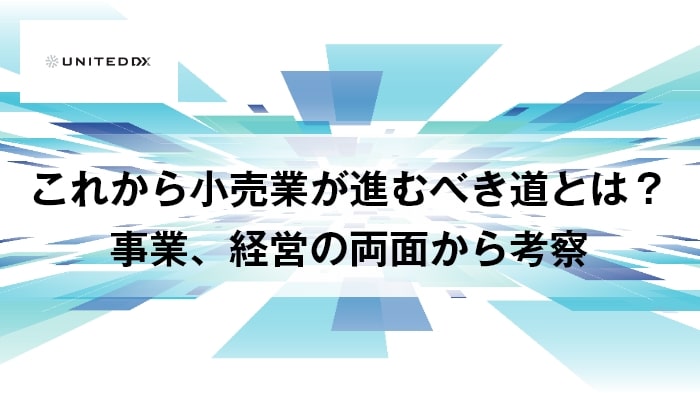
小売業界は、コロナ禍を経て二極化の様相を呈しています。一方は、店舗のオンライン化や業務のデジタル化、そこから得られるデータと施策を連動させて業績を上げている企業。そしてもう一方は、本格的なデジタル化に踏み切れず、リアル店舗の売上減少に引っ張られる形で業績が低下している企業です。
今回は、これまでユナイテッドで社外のエキスパートの方たちとおこなってきた対談をもとに、小売業界におけるDXの現状と、DX推進の際に事業面・経営面でそれぞれ気を付けるべきポイントを解説します。
小売業DXの現状
人々の価値観や嗜好が多様化し、顧客のニーズも複雑化してきています。この変化は、コロナ前から起こっていましたが、実際のところ小売業界でサービスをアップデートできている企業は多くありませんでした。ところが、コロナによってデジタル化が加速、DXを進められない企業は淘汰されかねない環境になっています。
現在に至るまで多くの企業がEC化、それに伴うDXを進めようとしています。小売業のDXによる変化は、大きく3つに分けられます。
1つ目は「顧客の囲い込み」です。既存顧客に対し、デジタルプラットフォームを介してコミュニケーションを取ってエンゲージメントを高める施策です。具体的にはポイントなどの継続的なインセンティブの付与や、ピンポイントでの情報配信などがあります。
2つ目は「接客の高度化」です。対面での接客のみならず、リアルとデジタルのハイブリッドでの接客、またはデジタルのみでの接客も進んでいます。
3つ目に「新たなUXの創出」。これまでにないような新しい顧客体験を提供することです。
これら3つを組み合わせて顧客体験をつくることが極めて重要です。「大量生産時代」から「顧客体験の時代」に突入しており、良質な体験を提供しない企業は生き残っていけません。
事業視点におけるDX推進のポイント
このような時代の変化の中で、「D2C」というビジネスモデルが急速に広がっています。店舗やWeb、SNSで消費者と直接接点ができるため、事業者と消費者の距離が近く、ファン化を進めやすいビジネスです。顧客との距離の近さが魅力なので、企業と顧客の双方向の関係性をいかにつくるかがカギとなっていくでしょう。そのため、業界内の競合のみならず、他業界のDX成功事例を参考にすることも考えておく必要があります。
また、前述した3つのポイントを押さえてオンラインでの顧客接点をつくることにより、記憶に残るD2Cブランドとなることができますが、今後はより、リアル店舗の価値が問われる時代になってくると予測されます。オンラインだけで展開するよりもリアル店舗を持った方が、成長速度が上がるケースも多いからです。
オンライン店舗が普及したいま、リアル店舗の役割は、効率性・利便性を高めて購買を促すことではありません。スマホが普及して以降、効率化や利便性は、主にECが担うようになりました。スマホ1台あれば、自宅から商品を購入することができます。移動時間や滞在時間を短縮し、購買を効率化できるだけでなく、リコメンドという形で利便性も向上させることができるようになりました。
そんな中でリアル店舗がおこなうべきことは、購買に「付加価値」を与えることです。つまり、「楽しい買い物体験」を演出するのです。「家族や恋人と買い物に行く」といったことは、リアル店舗ならではの体験になります。このような、人とのつながりや買い物のプロセスに価値を与えていく工夫が求められています。
リアル店舗のもう1つのメリットは、顧客の解像度が上がる点です。リアル店舗で接客を通して得る顧客情報は、オンラインで得る定量的なデータ以上に貴重な情報となり得ます。接客の中で得た課題やニーズを、よりよい商品開発や顧客体験に生かしていくのです。
リアル店舗におけるリッチな顧客体験のためのファーストステップにオンライン店舗を活用するという施策も多く取り組まれていくと考えられます。その中で1つ注意すべき点があります。リアルの体験価値を高めようとすればするほど、1顧客あたり、1商品あたりのコストが上がってしまうことです。それでもリアルの体験価値を重視していくためには、別の収益モデルが欠かせません。つまり、DXによってきちんと収益を確保することです。
DXに取り組んで業務効率化を進めることで収益を確保する一方で、リアル店舗は効率化では提供できない顧客価値を提供していく。この両輪がシナジーを起こすことで、短期目線での収益を上げながらも、長期目線で見た時に重要となる、たくさんのファンをつくることもできるでしょう。
企業によっては、必ずしもD2Cを展開する必要はありません。ですが、今成功している企業の多くは、社会課題意識が高く、自分たちの存在意義(パーパス)を広く打ち出しています。「ビジョン」と「顧客体験」。この2つに意識的になることは生き残っていくために重要なポイントです。
経営視点におけるDX推進のポイント
ここまで、事業戦略の視点からDX推進のヒントを探ってきました。次に、経営視点から、どのようにDXを進めていくべきかを考察します。
企業によって、DXの位置づけはそれぞれです。全社的なプロジェクトとしてDXをすべての事業に適用しようとする企業もあれば、既存事業はそのままに、新規事業としてDXを考える企業もあります。ただ、DXは、業務を効率化させる手段であるため、全社で取り組むことが望ましいと言えます。
全社レベルでDXを推進するためにまず必要なのは、「なぜやるのか」の定義です。そのために、先述した「ビジョン」「顧客体験」を再考する必要があるのです。「誰に、何を提供する」という会社の存在意義が明確になれば、全社戦略としてDXが必要であるという結論に行きつくことができるのではないでしょうか。
大企業であればあるほど、会社の変革を担うメンバーはマイノリティとなり、社内からの反発も大きくなりやすいでしょう。だからこそ、重要なのは経営層のマインドセットです。経営陣がどこまで腹を据えられるか。その覚悟がDXによる変革のカギを握ります。
経営層が積極的に社外との情報交換やコミュニケーションをおこない、知見を溜めていく作業も欠かせません。
経営陣にこういったマインドが求められる一方、DXにつながるアイデアを出す若手社員の側にも、工夫の余地はあります。新しい取り組みを提案する際の弱点は、エビデンスが少ないこと。そこを補うために、未来のビジョンをビジュアル化・ストーリー化して伝えることが大切です。
人は言葉やロジックだけで語られるより、具体的な画が見えた方が納得しやすいものです。そうやって経営層にも社内のステークホルダーにも、このような工夫を凝らして事業の妥当性(リスクの小ささや実現可能性の高さ)を伝える。ここが非常に難しい、かつ重要なところです。
変革の実行の段階に入ると、企業は縦と横の関係に悩むケースが多々あります。既存事業を軸とした縦の関係、機能変革としてのDXは横の関係です。変革初期の多くは、既存事業、つまり縦の関係が強いため、その力関係のバランスをうまく取った計画を策定します。
具体的には、既存事業の事業部がイニシアティブをとる取り組みと、DX推進側がイニシアティブをとる取り組みに分けるのも1つの手です。変革中期~後期にそれを一本化することで、スムーズな移行を実現している企業もあります。
注意点としては、これらのプロセスを、全て外部のコンサルティング企業に丸投げしてしまうと、社内にノウハウがたまらず、本質的な変革につながらないことです。初めは外部のプロフェッショナルを活用しつつも、知見を身に付けた人材を育てていく必要があります。
このような流れで、成果を出しながら成功サイクルを生んでいくことが、DXによる変革遂行のために不可欠です。
〈参考記事〉
・ユナイテッド、「≪小売業の変革を目指す≫FABRIC TOKYO流 D2Cの心得」
・ユナイテッド、「大手小売店のDXを徹底解剖~最先端事例から紐解くあるべき姿~」
・ユナイテッド、「~トップの覚悟が会社を変える~味の素株式会社CDOが語るDX成功の秘訣」
この記事の著者
ユナイテッド株式会社
ユナイテッドは、企業のDXによる変革を支援する「企業のトランスフォーメーション」、DX人材を輩出する「個人のトランスフォーメーション」を推進し、双方のマッチングも行うプラットフォームとして、社会のDXを推進します。
https://united.jp/
ユナイテッドは、企業のDXによる変革を支援する「企業のトラン...
