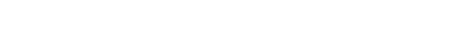広告運用においてビジネスの成功を測る基準であるKPI。しかし、KPIを達成したにもかかわらず、事業成果に結びつかないという悩みを抱える方も少なくありません。Hakuhodo DY ONEとMeta日本法人Facebook Japan(以下、Meta)はパートナー連携を強めながら、広告運用の知見を蓄積してきました。広告運用のKPIのみならず、その先にある事業目標を達成するという共通の目標を追求する中で着目したのが、ミドルファネルへのアプローチです。Meta広告を通じて事業成果を拡大するための効果的な方法について、Hakuhodo DY ONEの高橋佐世子、鈴木良太、Metaの河村拓氏に聞きました。
ミドルファネル攻略とは
- デジタル広告施策をおこなっているにもかかわらず、事業成果に結びつかないと悩む広告主が少なくないと聞きます。

左から、Hakuhodo DY ONE 鈴木良太、Hakuhodo DY ONE高橋佐世子、Meta日本法人Facebook Japan河村拓氏
高橋:デジタル広告施策が事業成果に結びつかない理由の一つは、ロワーファネル施策とアッパーファネル施策の分断にあります。よくある例として「アッパーファネル施策でブランドリフトは実現できても売上との相関が見えない」、「ロワーファネル施策における新規顧客獲得が頭打ちとなり、事業がスケールしない」などの課題が挙げられます。ロワーファネル施策、アッパーファネル施策の双方をおこなっている広告主でもそれぞれの施策が別々におこなわれ、全体として事業成果に十分に結びついていないケースもあります。
河村氏:当社においても広告主と向き合う中で、アッパーファネルとロワーファネルへの両アプローチの間が分断しているキャンペーンが少なくないことに気づきました。二つのアプローチの間を埋める施策や指標の不足が課題となっています。
また、現在、生活者の行動において、商材とのタッチポイントが多様化し、複数のメディア接触が当たり前になっています。単純にマーケティングファネルの上から下に落とすという考え方だけでは通用しないケースが増えているため、ブランドや商品とのエンゲージメントを濃くすることが大切になってきています。

- アッパーファネル施策とロワーファネル施策で分断が生まれるのはなぜなのでしょうか。
鈴木:要因の一つには、いわゆるミドルファネルをうまく攻略できていないことが挙げられます。ミドルファネル攻略とは、アッパーファネルとロワーファネルの施策を統合しながら、アッパーファネルからロワーファネルへと移る中間段階で生活者とのエンゲージメントを強化する手法です。
高橋:ミドルファネル攻略は、事業成果を拡大するための戦略でもあります。ロワーファネルへのアプローチに偏ると事業成果が縮小してしまいますし、逆にアッパーファネルだけを狙っても成果に結びつきにくい。アッパーファネルのボリュームを拡大しながら、確実にロワーファネルでの獲得につなげていかなければなりません。このミドルファネル攻略こそが、Web広告を事業成果に結びつけるために必要不可欠です。

河村氏:ミドルファネル攻略では、アッパーファネル施策のような一方向のメッセージだけでは不十分で、生活者とブランドとの関係構築が重要です。なぜなら、ただブランドを認知してもらうだけでなく、購買の選択肢の一つとしてブランドを考慮してもらうためには、生活者のTop of Mind※に入る必要があるからです。その点においてMeta広告は有効なミドルファネル攻略手法の一つだといえます。
※Top of Mind …生活者が特定のカテゴリーで商品やサービスを考える際に、最初に思い浮かべるブランドのこと。
Meta広告がミドルファネル攻略に有効な理由
- Meta広告がミドルファネル攻略に有効な理由を教えてください。
河村氏:まず、InstagramやFacebookはそもそものメディア特性として、「好き」という気持ちや「欲しい」と思わせる興味喚起と親和性が高いからです。ユーザーは日常的に好きなタレントやブランドをフォローし、「いいね」やDMを通して、積極的にインタラクションを起こしています。
高橋:昨今は、「推し活」など好きなものを応援する気持ちが生活者の購買行動に大きく影響しています。ロワーファネル施策とアッパーファネル施策をつなぐミドルファネル攻略をおこなう際には、InstagramやFacebookなどを活用し、こうした「好き」や「推し」のシグナルをキャッチすることが有効です。
河村氏:そして広告では、「認知度」、「トラフィック」、「エンゲージメント」、「リード」、「アプリの宣伝」、「売上」の6つの広告の目的を用意しており、ファネルごとに最適化を促すことができます。
加えて、広告クリエイティブにおいて多様な表現方法が可能であることも、ミドルファネル攻略に有効な理由の一つです。

鈴木:一般的に、アッパーファネル層向けのクリエイティブではブランドメッセージを強調することが多く、ロワーファネル向けクリエイティブでは価格訴求など行動直結型のメッセージがしばしば用いられます。それに対し、ミドルファネルに対しては日常生活における具体的な利用シーンを示しつつ、実生活の課題や欲求に的確に応える内容が求められます。なぜなら、このようなクリエイティブは、生活者とのエンゲージメントを強め、ブランドを生活者のTop of Mindに位置づけられる可能性を高められるからです。

河村氏:Meta広告のクリエイティブにおける構成要素はさまざまです。広告のフォーマットとして静止画や動画があり、配信面にはフィード 、ストーリーズ、リールなどがあります。特にフォーマットに関しては、ストーリーズやリールなどとの親和性が高い縦型動画の重要性が増しています。こうした縦型のショート動画の台頭により、通常の動画・静止画だけでは難しかったリッチな表現方法が可能になりました。加えて、Meta広告ではパートナーシップ広告 を活用したインフルエンサー施策も実施でき、企業とクリエイター両方の視点で発信できるようになっています。
これらの広告フォーマットや配信面、訴求軸、クリエイター起用のありなしなどの要素を掛け合わせることで、多様なクリエイティブのバリエーションを確保することができ、ターゲットとしたいミドルファネルに最適なクリエイティブの展開が可能となります 。
高橋:パートナーシップ広告は、当社においても近年特に高い成果を確認しているメニューです。パートナーシップ広告とは、企業やブランドがインフルエンサーやクリエイターと連携して商品やサービスを訴求するメニューです。加えて、ユーザーが生成したコンテンツを模したUGC風クリエイティブも高成果が期待できます。これらのクリエイティブは、ロワーファネルからの信頼を得ているクリエイターの投稿を通じて発信されていたり、具体的な利用ケースを示したりできるため、生活者の高いエンゲージメントが期待できます。

ミドルファネル攻略成功には中長期的なPDCAが必要
- ミドルファネル攻略で重要なことは何なのでしょうか。
鈴木:ミドルファネルを攻略するためには、中長期の視点でPDCAサイクルを回すことが大切です。たとえば、まずミドルファネルユーザーがどのような興味関心層にいるのかを探るために、テストとして複数のインフルエンサーを起用します。そして成果を上げたインフルエンサーを見つけたら、次回のキャンペーンではそのインフルエンサーに類似したキャスティングをおこなうのです。
一回の施策でミドルファネルにアプローチしようとする企業もあるかもしれません。しかし、ミドルファネルユーザーがどのような興味関心層に存在するのかを検証するには、アプローチを少しずつロワーファネルからミドルファネルへ広げたり、アッパーファネルからミドルファネルへと落とし込んだりすることが必要で、それにはある程度の時間がかかります。
高橋:広告運用のPDCAサイクルの主な要素として、KPIの設定、クリエイティブ制作、効果検証が挙げられます。これらを操作することでミドルファネルへ効果的にアプローチできるのですが、こうした要素において多くのマーケターが課題に直面します。

ミドルファネル攻略で直面しやすい課題
- 具体的にどのような課題にぶつかるのでしょうか。
高橋:まず、ミドルファネルの定義が本質的に曖昧であることから、KPIの整理が困難です。マーケティングファネルにおける「ミドルファネル」には多様なユーザーの心理や行動が含まれています。ミドルファネルは情報を収集しつつ意思決定を進める段階にあり、その状況は変化しやすいからです。この段階のユーザーの多様性を考慮すると、KPIを一律に設定することが難しいといえます。
また、ミドルファネル向けキャンペーンのKPIは中間指標です。そのため、設定したKPIが実際の購買行動に結びつくのか、さらには事業全体の成果にどの程度影響を与えるのかという証明が困難で、KPIの妥当性に確信を持ちにくいという課題もあります。

- PDCA要素の二つ目として挙げたクリエイティブ観点ではどのような課題がありますか。
鈴木:クリエイティブ制作に関しては、なかなか大きなリソースを割けないという声をよく聞きます。先ほど河村さんがお話しされていた通り、Meta広告の特徴を生かすにはクリエイティブの本数とバリエーションを確保することが重要です。またロワーファネルやアッパーファネル向けとは異なるメッセージングも必要になります。しかし、企業がそのための専門知識やスキルを整えるのは容易ではありません。

- 効果検証の難しさはどのようなところにありますか。
高橋: Meta広告の効果を正しく検証できないという悩みを抱える方が多くいらっしゃいます。FacebookやInstagramは情報収集や暇つぶしの目的で利用されることも多いプラットフォームです。Meta広告は、このような生活者のモチベーションを阻害しない形で広告が表示される利点がある一方、検索広告などと比べると、すぐには購買に結びつかないこともあります。
でも実は、Meta広告を通じて認知したブランドが、その後、購入されるケースは多いです。このような間接的な効果は、数値化が困難です。それにもかかわらず、ミドルファネルをターゲットとした広告施策の場合、この間接効果の評価が求められます。
鈴木:インフルエンサーを活用した広告で悩みがちなのが、どのインフルエンサーが実際の事業成果に結びついたかという分析です。Meta広告の管理画面では、リーチやインプレッション数、クリック率などの基本的な指標は確認できますが、それ以上の詳細な分析は難しいのが現状です。たとえば、特定のターゲット属性と相性の良いインフルエンサーの特定や、ブランドリフトに効果的だったインフルエンサー、実際の来店や購買につながったインフルエンサーの判別などは管理画面からは分かりません。しかし、ミドルファネル攻略では管理画面の指標とは異なるKPIを設定することが多いため、こうした詳細な分析がより重要になってきます。

こうしたミドルファネル攻略における課題に対し、当社とMeta社は協業しながら解決方法を模索してきました。
<プロフィール>
Meta日本法人Facebook Japan
エージェンシーパートナー
河村拓

2016年に電通入社、ストラテジックプランナーとして活動。その後、外資系の事業会社を経て、Facebook Japan (現Meta)に入社。Metaでは、ブランド領域のソリューション担当としてプランニングを経験したのち、異動。現在は、代理店パートナーシップチームに所属し、代理店とのMetaを活用した事業戦略の構築や事業開発、クリエイティブやAIに関するソリューション導入のサポートに従事。
この記事の著者
DIGIFUL編集部
「DIGIFUL(デジフル)」は、株式会社Hakuhodo DY ONEが運営する「デジタル時代におけるマーケティング」をテーマにした、企業で活躍するマーケティング担当者のためのメディアです。
当社がこれまでに得たデータや経験から、具体的事例・将来展望・業界の最新注目ニュースなどについて情報を発信しています。ニュースやコラムだけでなく、日常業務や将来のマーケティング施策を考えるときに役立つダウンロード資料や、動画で学べるウェビナーコンテンツも随時追加していきます。
デジタルマーケティングの最新情報や知見を得るための信頼できる情報源の1つとしてお役立てください。
「DIGIFUL(デジフル)」は、株式会社Hakuhodo ...
高橋 佐世子
2014年、デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会社(現 株式会社Hakuhodo DY ONE)に入社。メディアコンサルティング担当として、ソーシャルメディア、出版メディア等を担当。専門的な知識や経験を軸に、サイトコンサルティングや広告商品開発などにも携わり、未来を見据えてビジネスチャンスの拡大を目指す。特にSNS領域においては、メディアコンサルティング領域の立ち上げをリードし、グループ全体のビジネス推進に寄与。現在はインフルエンサーマーケティング領域において、各プラットフォーマーとの連携によるサービス開発を遂行している。
2014年、デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム株式会...
鈴木 良太
ネット専業広告会社でのクリエイティブプランナーを経て、株式会社アイレップ(現 株式会社Hakuhodo DY ONE)へ入社。入社後はメディアプランナーとして従事し、メディアを横断したフルファネルの企画立案や調査設計をおこなってきた。メディアそれぞれの特性に合わせた細やかなユーザーコミュニケーション設計を得意とする。
ネット専業広告会社でのクリエイティブプランナーを経て、株式会...