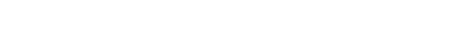月間利用者2,300万人を誇る「メルカリ」(2025年5月時点)。国内で高い知名度を誇るメルカリが、2024年に、ライフタイムバリューの期待値が高いZ世代のマーケティングを推進する「GenZ(ジェンジー)プロジェクト」を始動しました。18歳から24歳までのZ世代ユーザーにピンポイントでアプローチし、事業成果を達成したこのプロジェクトには、ターゲット理解、メディア選定、クリエイティブ効果検証など、Z世代マーケティングにおけるいくつものヒントがありました。本記事では、Z世代マーケティング成功のヒントについて、「GenZプロジェクト」をともに推進した、株式会社メルカリ Marketplaceマーケティングスペシャリスト 今岡駿介氏(以下、メルカリ今岡氏)とMeta日本法人Facebook Japan エージェンシーパートナー 河村拓氏(以下、Meta河村氏、株式会社Hakuhodo DY ONE Webディレクター 諸木茉衣(以下、諸木)が実際の取組みを振り返りながらお伝えします。
※本稿は2025年5月27日にMeta日本法人Facebook Japan主催のMeta Festival Japan 2025 for Agenciesにておこなわれた講演「メルカリのZ世代戦略で実践したMeta施策のクリエイティブアプローチと設計」をもとに作成しています。
※本記事の一部は、当社内で開発・運用する生成AIツール「HAKUNEO」を活用して生成しています。なお、最終的な記事内容の確認・編集はDIGIFUL編集部がおこなっています。
Z世代に特化したマーケティング「GenZプロジェクト」を始動
Meta河村氏:メルカリでは「GenZプロジェクト」を立ち上げ、Z世代に特化したマーケティングを推進していますが、プロジェクト立ち上げの背景を教えてください。
メルカリ今岡氏:メルカリは、これまでもお客様の拡大を目指してデジタルマーケティングを実施してきたこともあり、この12年で月間利用者数は2,300万人に成長しました。幅広いお客様にサービスをご愛用いただいています。しかし、ユーザー層が多様になってきたことで、これまでのマーケティング施策ではリーチしづらい層が出てきてしまっていることに課題を感じていました。特にリーチがしづらい層として、Z世代を中心とする若年層が挙げられますが、この層は、長期的なサービス利用が見込めます。また、トレンドの中心にいる世代でもあるため、Z世代を将来的な成長に大きく貢献する重要なターゲットと位置づけました。こうした背景から、2024年に「GenZプロジェクト」を始動することとなりました。
従来は新規会員獲得全体をKPIとしていましたが、このプロジェクトではZ世代の新規会員登録数を明確なKPIとして設定し、マーケティング戦略を練り直しました。
成果を伸ばし続けるカギはクリエイティブの高速PDCA
Meta河村氏:Z世代向けのマーケティング戦略は、どのように推進されたのでしょうか?
諸木:中長期視点では[配信準備期][配信初動期][配信拡大期][配信安定期]と大きく4つのフェーズに分けてプランニングをおこないました。[配信準備期]では、ユーザーのメディア利用実態分析からZ世代のインサイト理解を深め、そのうえで配信媒体の整理を実施。[配信初動期]以降では、配信設計の見直しなど、運用戦略の微調整をしながら施策を実施しました。さらに、クリエイティブ検証も並行してスタートし、運用戦略とクリエイティブ両軸でPDCAを回していきました。特にクリエイティブは、効果が見込めそうな訴求ポイントを網羅しつつ、カテゴリや演出の検証を進めていき、勝ち要素が見えてきた段階で、生成AIを活用したクリエイティブの拡充・量産を進めました。さらに、クリエイティブが摩耗しないように成果を維持しながら新しいアプローチも模索するなど、仮説検証のサイクルを高速で回し、成果を残せるクリエイティブを見極めながら展開していくアプローチを採用しています。

Meta河村氏:運用体制についても工夫されたとのことですが、詳しく教えていただけますか?
諸木:Metaはクリエイティブ一つの成果貢献度が大きい媒体なので、定量的な基準を設けた上でクリエイティブの勝ち負けをしっかり判断していくことが重要です。明らかになった勝ち負けの分析をもとに、常に次のアクション方針を運用チームとクリエイティブチームで連携してアジャイルに策定していくことで、直近の成果状況を踏まえたクリエイティブ施策ができるようになりました。特に重要なのは、データに基づいて素早く判断し、次の一手を打っていくスピード感です。クリエイティブと運用の両チームが密に連携することで、効果的なPDCAサイクルを実現することができました。
Z世代へのアプローチがしやすいInstagramで面ごとのコミュニケーションを設計
Meta河村氏:GenZプロジェクトでは、Instagramを主な配信先として選定されています。なぜ、Z世代マーケティングにInstagramを選んだのでしょうか。
諸木:選んだ理由は二つあります。一つ目はInstagramがZ世代にとってのメインメディアであること、二つ目は多様な配信面があることでコミュニケーション設計の柔軟性が高いという点です。
当プロジェクトを進めるにあたり、当社のZ世代社員を対象にアプリ利用状況をおこなったところ、Instagramの利用率が非常に高く、スクリーンタイムを見ても利用時間が長いことがわかりました。InstagramはSNSの中でも特に「魅力的なものやことを見つけるため」に利用されるメディアとして知られています。そのため、広告を打ち出す際も単にサービススペックを提示するのではなく、魅力的な情報コンテンツとして広告を配信することで、自然な動線でコンバージョンまで導きやすいという特徴があります。
また、Instagramは配信面によってユーザーモチベーションが異なるため、配信面の使い分けをすることで細やかなコミュニケーションを可能にします。フィード面は情報収集モチベーション、Instagramリールや、Instagramストーリーズ面はエンターテインメントモチベーションを持つユーザーが集まるので、クリエイティブを作り分けることで多様なユーザーへ適切なアプローチができるのです。

メルカリ今岡氏:メルカリではさまざまな媒体を活用してきましたが、運用の最適化だけでは限界を感じつつありました。媒体によってはハードターゲティングで年齢指定ができるなど細かいオーディエンス設定はできますが、ターゲットを絞りすぎるとリーチできる母数が少なくなってしまうという課題がありました。Instagramは、Z世代の利用率の高さや、配信最適化を含む配信ロジックが非常に優秀だと考えていました。配信面ごとにクリエイティブが細かく分析・評価できるため、PDCAを回しやすいという観点でもInstagramが最も有力でした。
クリエイティブ制作は、ターゲットのインサイトを捉えるところから始まる
Meta河村氏:Z世代向けのクリエイティブを制作する上で工夫されたポイントを教えてください。
諸木:最も工夫したのは、制作着手前にクリエイティブ制作の土台作りをした点です。プロジェクト始動当初は、プロジェクトメンバーそれぞれが持つZ世代の印象にずれがあり、クリエイティブ制作が難航する場面もありました。そこで、「インサイト分析」「デザインマップピング」「GenZ座談会」を実施し、ターゲットのインサイトを洗い出してからクリエイティブ制作の土台を構築しました。これにより、クリエイティブの制作体制や共通言語の整備によるコミュニケーションエラーの減少やターゲットの深い理解など、細かい障壁が解消されて、プロジェクトメンバーが一丸となって施策に向き合うことができました。
三つの土台作りのなかでも、「GenZ座談会」の実施価値は非常に高かったと思います。座談会では、Z世代の大学生をお招きしてインタビューを実施、そこから得たインサイトを多方面から掘り下げ、最終的に企画の絵コンテを作成するワークショップを実施しました。インタビューを通じて、「コスパよりもタイパ(時間効率)を重視する」など、直接聞くからこそ見えるリアルなZ世代を体感することができ、GenZプロジェクトメンバーのターゲット解像度がぐっと引きあがるきっかけとなりました。このワークショップで作り上げた企画はいくつか実際に制作され、成果にも貢献しています。
Meta河村氏:Z世代特有のインサイトとして見つけられたものがあれば、具体例を教えていただけますか?
諸木:座談会を通して見えてきたZ世代特有のインサイトを2点紹介します。一点目が先ほど触れた「コスパよりタイパを重視する」というインサイトです。
SNSの普及によって、いつでも手軽にコンテンツを消費できる時代になったことから、ドラマや映画を倍速で視聴するなど、とにかく無駄なことをしたくないという傾向が見られました。メルカリにおいては、単に面倒だから出品しないのではなく、タイパを重視するがゆえに出品という行為そのものに機会損失感を覚えるユーザーがZ世代には一定数いることがわかりました。
二点目は「流行には乗りたいけれども、お金をかけすぎたくない。一度きりの買い物はメルカリで良い」というインサイトです。Z世代にとってトレンドアイテムは非常に重要ですが、トレンドアイテムや参考書など一度しか使わないようなものは、特にコスパを重視する傾向が見えました。
Meta河村氏:今岡さんも座談会に参加されたとのことですが、なにか新しい発見はありましたか。
メルカリ今岡氏: Z世代自体がかなり限定的な層であることから、ユーザーの解像度を上げていく必要性を課題として感じていました。デスクリサーチでZ世代の行動や広告に対する考え方は調べていましたが、「本当にそうなのか」という疑問や、成果が出た施策の再現性があるのかという点が言語化しづらい状況でした。ですので、GenZ座談会を通して、Z世代が抱く広告への印象や興味関心などのリアルな声を知れたのは大きな収穫でした。
生成AIの活用により、最短距離で訴求方針を最適化
Meta河村氏:実際に制作されたクリエイティブについて、生成AIの活用も含めてご紹介いただけますか?
諸木:訴求ポイントを網羅しつつ、どんなカテゴリが効果的か、どんな演出が効果的かを知るために、幅広い仮説をいくつか設定し、制作を進めました。結果、トレンドアイテムやファッションアイテム、Vlog調の演出が強い価値を持つことがわかり、本配信のクリエイティブでは、「おすすめポイントその1は、材料を安く揃えられるところ」「おすすめポイントその2は、使っていない作品が売れるところ」といった具体的な価値訴求や、「ワイヤレスイヤホンなくした!」といった日常的な困りごとからメルカリの価値を伝えるアプローチなどを展開しました。なかには、仮説検証の結果から、“冒頭5秒以内に詳細やサービス名を含む”という、縦型動画の常識を逆行したクリエイティブにも挑戦しましたが、意外にも成果が良く、Z世代にとっては魅力的な情報コンテンツであることが重要ということがわかりました。

また、生成AIを活用することで、これまでハードルが高かった表現や作成時間を要していた表現もできるようになりました。たとえば、メルカリに出品される商品にはイヤホンやトレーディングカードなど、他社商品が多く存在します。ユーザーの心を動かすには出品物の想起を促すクリエイティブが有効ですが、それをそのまま広告クリエイティブに使用することはできません。生成AIを活用すれば、ワイヤレスイヤホンのイラストや架空のトレーニングカードのイメージを短時間で作成できます。これにより、表現の幅が広がり、制作時間も短縮されるため、PDCAを回せるようになり、ターゲットに効果的なクリエイティブを開発しやすくなりました。
メルカリ今岡氏:メルカリのクリエイティブは、世の中で生成AIが商業利用されはじめた当初からプランニングやビジュアル面まで幅広い領域で積極的に活用しており、生成AIの活用を開始してからこれまでに制作したクリエイティブの約半数以上※は生成AIを使用しています。GenZプロジェクトではクリエイティブ制作やPDCAのスピードが非常に早かったのですが、これまでの広告運用でも積極的に生成AIを活用していたことで、社内の環境整備や体制がすでに整っていた点は成果実現における大きなポイントだったと思います。
※クリエイティブ制作過程の一部でも生成AIを活用したものを含んでいます
Z世代の新規利用層拡大とCPAの大幅改善を実現
Meta河村氏:プロジェクト全体の成果を教えてください。
メルカリ今岡氏:結論として、CPAが大きく改善し、予算を増やしながらもCPA自体も改善するという好循環が生まれました。その結果、KPIに掲げたZ世代の新規会員数は大幅に増加しています。
 冒頭で申し上げた通り、既存のデジタル戦略だけでは新規会員層が拡大しづらいという課題がありましたが、Z世代に向けて適切なクリエイティブでのコミュニケーションを実現し、最適な媒体を選定することの重要性を改めて認識しました。今回の取組みでZ世代の会員数が増え、データ量も蓄積されてきたことで、次の打ち手もしっかり打てるようになってきています。
冒頭で申し上げた通り、既存のデジタル戦略だけでは新規会員層が拡大しづらいという課題がありましたが、Z世代に向けて適切なクリエイティブでのコミュニケーションを実現し、最適な媒体を選定することの重要性を改めて認識しました。今回の取組みでZ世代の会員数が増え、データ量も蓄積されてきたことで、次の打ち手もしっかり打てるようになってきています。
Meta河村氏:今回の取組みを通して得た気づきを教えてください。
諸木:Metaは他のSNSと比較しても情報モチベーションを持ったユーザーが集まりやすいという特徴があります。そのため、魅力的な情報コンテンツの入り口を作ることが非常に重要です。Z世代に対しては特に、好奇心を呼び起こしたり、新しいアイデアを提示したりする工夫が効果的でした。たとえば「梱包」を訴求する場合でも、性別やターゲット層によって好まれる演出傾向が異なることがわかりました。

さらに、静止画においても商品素材やデザインを作り分けることで、同じ訴求でも男女それぞれの配信シェアをコントロールできることがわかりました。これはMetaの優秀なアルゴリズムがあってこそ可能になるターゲティングだと実感しています。

まとめ:Z世代マーケティングの成功要因
Meta河村氏:今回のZ世代プロジェクトの成功要因をまとめると、どのような点が挙げられますか?
メルカリ今岡氏:最も大きな成功要因は、Z世代のインサイトに基づいたクリエイティブ戦略と、それを効率的に量産・検証できる体制を構築できたことだと思います。特に生成AIの活用によって、クリエイティブのバリエーションを増やし、検証サイクルを高速化できたことは大きな強みになりました。
諸木:確かに、ターゲットインサイトの深掘りは今回の成果にとって重要なポイントでした。「クリエイティブは新たなターゲティング手法」といっても過言ではないくらい、ユーザーの心を動かす力を持っています。適切なクリエイティブを作ることで、ターゲットに対して自然なアプローチをすることが可能になります。Z世代は特に広告に対する目が肥えているため、彼らの心に響くコンテンツを提供することが何よりも重要です。
また、GenZプロジェクトにおいては、プロジェクトメンバーが一丸となってインサイト発掘から制作、検証までのサイクルを迅速に回せたことも大きな成功要因だったと思います。
Meta河村氏:ありがとうございました。これまで、さまざまなInstagramの広告配信をサポートしてきましたが、インサイト分析を起点としてクリエイティブ制作に落とし込んでいくプロセスは、認知施策で導入されることが多く、獲得領域ではとにかく量産して勝ち素材に絞っていくケースが多い印象にありました。しかしメルカリ様のような獲得領域が中心のキャンペーンにおいても、深いインサイト起点でのクリエイティブがここまでダイレクトにパフォーマンスに寄与することができるということは当社としても新たな発見でした。
サービスに関するご不明点やご相談がありましたらお問い合わせよりご連絡ください。
<プロフィール>
株式会社メルカリ
Marketplace マーケティングスペシャリスト
今岡駿介

2018年4月に新卒で広告代理店に入社。事業会社を経て、2024年7月にメルカリに入社。 新卒からデジタルマーケティングに携わり、現在はメルカリのアプリマーケティングに従事。
Meta日本法人Facebook Japan
エージェンシーパートナー
河村拓

2016年に電通入社、ストラテジックプランナーとして活動。その後、外資系の事業会社を経て、Facebook Japan (現Meta)に入社。Metaでは、ブランド領域のソリューション担当としてプランニングを経験したのち、異動。現在は、代理店パートナーシップチームに所属し、代理店とのMetaを活用した事業戦略の構築や事業開発、クリエイティブやAIに関するソリューション導入のサポートに従事。
この記事の著者
DIGIFUL編集部
「DIGIFUL(デジフル)」は、株式会社Hakuhodo DY ONEが運営する「デジタル時代におけるマーケティング」をテーマにした、企業で活躍するマーケティング担当者のためのメディアです。
当社がこれまでに得たデータや経験から、具体的事例・将来展望・業界の最新注目ニュースなどについて情報を発信しています。ニュースやコラムだけでなく、日常業務や将来のマーケティング施策を考えるときに役立つダウンロード資料や、動画で学べるウェビナーコンテンツも随時追加していきます。
デジタルマーケティングの最新情報や知見を得るための信頼できる情報源の1つとしてお役立てください。
「DIGIFUL(デジフル)」は、株式会社Hakuhodo ...
諸木 茉衣
2023年4月入社。大学時代はSNSマーケティングの会社で約9ヶ月間、Instagram投稿の制作を担当するなどデザイン制作にも従事。現在は獲得領域のWebディレクターとして、フリマアプリ商材から自動車保険商材、不動産商材まであらゆる業種を担当。
2023年4月入社。大学時代はSNSマーケティングの会社で約...