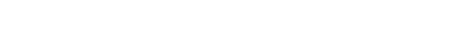こんにちは、Search&Feed本部の森戸です。株式会社アイレップ(現 Hakuhodo DY ONE)に新卒入社後、10年以上にわたり検索連動型広告をはじめとする広告運用に携わってきました。2016年から社内での運用専門研修において講師も担当しています。プロフィールによると、どうやら「卓越したスキルと独自の語り口で、社内外どちらからも頼られる運用のプロフェッショナルとして唯一無二の地位を確立」しているようなので、その志で広告運用に向き合っています。
2025年9月9日、Google 検索における「AI モード」の日本語提供が開始されました。この新機能によるマーケティング全体への影響や、企業に求められる新たな戦略については、前記事「Google検索『AI モード』の日本語対応と、マーケティングへの影響」で解説されています。本記事では、「AIモード」が広告運用にどのような影響を与えるのか、検索連動型広告に焦点を当て考察したいと思います。
参考:Google、「Google 検索における『AI モード』を日本語で提供開始」、Google Japan Blog、2025年10月23日閲覧
改めて「AI モード」とは何か?
「AI モード」とは、AIが検索ユーザーの意図や文脈を汲み取り、複数の情報ソースを参照したうえで、従来の「リンクの一覧の提示」ではなく会話的かつ体系的な回答として返してくれる、新しい検索体験です。「Google検索「AI モード」の日本語対応と、マーケティングへの影響」でも解説されている通り、米国での調査結果によれば、従来のGoogle 検索と比較して主に次のような特徴がみられます。
- 複雑な問いに対して「AI モード」が選ばれやすい
- 生成された回答のみでユーザーのニーズが満たされ、外部サイトに遷移せずに完結するケースが多い
「AI モード」を使ってみた個人的な所感
実際に「AI モード」を使ってみた個人的な所感としては、従来型の検索結果でみられる「AI Overviews」と回答内容は近いものの、AIによる返答が確実に得られる新たな受付窓口が追加されたことで、検索体験の幅が広がって豊かになったという感覚がありました。
従来型の検索は「既存の答え(正解)を調べる」目的に適していましたが、「AI モード」は、何かを比較・検討するなど、「自分の状況や希望に沿った、自分目線の最適な答えを導き出すことを重視する」場合に強みを持つと考えています。
たとえば、「今度の旅行はここに行って、このホテルを予約するぞ」「私は絶対にこの商品を買うのだ」とすでに諸々の意思が固まっている生活者にとっては、「AI モード」の回答は過剰・冗長になるケースもあるかもしれません。一方で、「旅行に行こうか行くまいか、行くならどこに行こうか」「何を買おうか、いや買わなくてもなんとかならないか」のように、まだ選択肢が多く情報収集をおこなっている段階の生活者にとっては、「AI モード」の検索結果は非常に有益な情報源となり得ます。
また、複雑な条件検索やオープンクエスチョンとも親和性が高いといえるでしょう。たとえば、私は最近暇さえあればおいしいカレーを食べに出かけています。平日に休みを取ったある日、「“平日だからこそ行くべきお店”を選べるのがベストだな?」と考え、
「土日が休みで禁煙の、都内の人気のカレー屋を教えてください。ちなみにカレーの中ではキーマが割と好きで、ほかにはシャバシャバ系より粘度があるタイプが好み。あとラッシー好きだから飲みたい」
と「AI モード」で検索し、お店をサジェストしてもらいました。結果、一部誤った内容もありましたが、従来型の検索ではなかなか表現しにくい複雑な要求を叶えられるので助かりました。
このように、質問の性質や情報収集のフェーズに応じて従来型の検索と「AI モード」を使い分ける動きは強まっていくと考えられます。「AIで検索したい人は、そもそもGoogleではなく、別のAIサービスを利用するのでは?」という見方もあります。しかし、長年「ググる」という文化に浸かり「検索するという行動は検索エンジンでおこなうものだ」と手癖が染みついている私のような人間からすると、従来型の検索のオプションとして同じプラットフォーム内でAI検索を完結できるのは利便性が高くスムーズなので、自然に使い分けが進むのではないかと予想しています。
「AI モード」における広告掲載とその運用はどうなっていくのか?
ここからは、「AI モード」に広告が今後どのように掲載され、運用がどう変化していくのかについて、私の個人的な将来予測も含めて考えていきます。
なお、米国ではすでに試験的な広告表示が始まっており、PCデバイスでショッピング広告やテキスト広告がAI生成による最初の回答の下に表示される形式が採用されています。AIによるレスポンス後に関連リンクとしてサジェストされる仕組みです。
参考:Google, “More opportunities for your business on Google Search”, Google Ads & Commerce Blog, Accessed 24 Oct 2025
参考:ITmedia、「Google、「AI Mode」と「AIによる概要」に広告掲載へ まずは米国のデスクトップで」、ITmedia NEWS、2025年10月24日閲覧
検索クエリの変化
上述の通り、従来型の検索から「AI モード」に移行する検索クエリ(検索語句)と従来型の検索に残る検索クエリが存在し、掲載枠の違いによって表示回数などの指標の変動が起こり得ます。
一般的に、使用単語数が多くなるような複雑な条件やニッチな条件での検索は、そもそもの検索ボリュームが大きくありません。こうした検索はこれまでも、検索語句レポートで個別の数値実績が確認できないものが多い傾向にあったため、広告運用上の直接的な影響は限定的かもしれません。しかし、「○○ 比較」のような検索ボリュームの大きい非指名的な検索が「AI モード」の多語検索へとシフトしていくとなると、影響は大きくなっていくでしょう。
「○○ 予約」など生活者側の意思が明確な検索クエリは、従来型の検索に残る可能性が高いでしょう。ブランド名やサービス名を含む指名検索も、「このサービスを使うのだ」という固い意思によるものとみれば「AI モード」への移行は限定的かもしれません。ただし、たとえば何も他の言葉を掛け合わせずに「社名・サイト名・サービス名のワード単体」で検索した生活者であれば、明確なサービス利用意思が固まっているとは限らず、「このサービスはどのようなものなのだろうか」という調査の意思で検索している可能性もあります。こうした場合は、調査・比較のための文章的な「AI モード」の検索クエリへと“転生”し、広告運用やブランディング戦略上で非常に重要な指名ワードについても無視できない影響を受けるかもしれません。
また、検索連動型広告の強みは「生活者が情報を欲しているときに、適切な動線を提示できる」点にあります。これまで、プラットフォーム側ではその生活者の行動履歴などのシグナルを用いているにせよ、広告の運用コンサルタント側が生活者の欲しているものを読み取るためのソースは検索クエリの文字情報でした(読み取れる情報が存在するという点それ自体が強みでもありますけどね)。
今後「AI モード」への広告配信機能が発展し、通常検索面との切り分けが運用上できるようになってくると、文字情報に加えて「深く調査しようとしているか」など「検索態度情報」が検索面の違いから推察できるようになり、運用戦略にも影響してくる可能性があります。たとえば、同じような検索語句であっても「AI モード」で検索された際にだけ広告でリーチすべきだ、といった運用判断が必要になることも考えられます。現在でも、Google 検索パートナーにYouTube検索結果面が含まれることで、「これは明らかにYouTube内で視聴する動画を探しているのだろう」というクエリを除外するような広告運用をおこなうケースがありますが、それに感覚は近いかもしれません。
広告運用施策で想定される変化
従来の検索連動型広告では、「検索した生活者にとって必要な情報が提供されている」と明示的にわかる広告が、生活者目線でも広告の品質評価アルゴリズムの面でも重要であり、その代表的な手法が「生活者の検索クエリと一致する文言を広告文に含める」ことでした。
しかしながら、「AI モード」では検索クエリがより複雑になり、会話的な独特の砕けた表現も増える傾向が想定されます。以前から、音声検索による会話調のクエリも一定数みられていましたが、広告運用へのインパクトはそれらを意識して扱うまでには至らない印象でした。ただ、今後「AI モード」の登場でそうしたクエリのボリュームが無視できなくなってくると、クエリ内の文言のシステマティックな挿入での広告品質の担保は相対的に難しくなってくるかもしれません。
その分、プラットフォームが文字情報以外のシグナルから判断する「生活者の関心・インテント」と、広告とのマッチングを適切にしてもらえるよう、「広告運用サイドが意図する背景情報」をプラットフォームに伝える必要が増し、広告文やランディングページも「ターゲティングを規定する情報」として捉えて設計する意識が今まで以上に不可欠になってくるのではないでしょうか。
現時点でも、Google 広告では「インテント マッチ」やキャンペーンの「AI 最大化設定」など、生活者の広いインテントに対応する機能が進化しており、これらを活用した運用が引き続きメインストリームとして重要でしょう。従来のLPO(ランディングページ最適化)はもちろんのこと、AIO(AI最適化)にもしっかり取り組むことが検索連動型広告の運用成果においても重要になってくるかもしれません。
将来的に「AI モード」における広告配信や、AI時代の検索連動型広告の仕組みはどうなっていってほしいか?
米国のテスト配信の例をみても、「AI モード」への広告掲載はまずテキスト広告やショッピング広告などの既存のフォーマットで開始されることが想定されます。しかし、ここでは中長期的な視点で「最終的にどのような形で広告が存在するのが良いのだろうか?」について、最後に私見を述べてみます。
私個人としては、「AI モード」における広告の在り方として、既存のテキスト広告のフォーマットによるアプローチというのは理想形ではないように思います。
従来の検索結果ページでは、生活者による検索のニーズに応じた候補のサイトがリストとして並び、その中に広告も自然に表示されるため、検索体験を大きくは阻害せずに広告配信が可能でした。一方AIによる検索体験では、質問に対しAIによる一つの統合的な回答が返ってくる形式です。もちろんその回答の中に多様な情報ソースがあったりニーズに応えうるサイトへの動線があったりするわけですが、とはいえ「一つのアンサーが提示される」という体験の中に「別の動線として広告が登場する」というのはどうしても検索体験にとってのノイズになりやすいでしょう。
また、「多角的な情報収集をし、客観的になるべく判断したい」というニーズで生活者がAIを利用している場合に、「そこにお金を投下して割り込んでくる広告」というものにネガティブな印象を受けるケースは、AIにすでに慣れ親しんでいる層にほど起こりやすい事象かもしれません。よって、いかに「割り込まれていない」感を持たせられる広告体験を設計できるかは重要なポイントといえるでしょう。
そのため、従来型の「検索体験内に溶け込んでいる」という要素を捨てて、完全に別のインターフェースとして動線を用意したり、配信される広告の内容自体が「めちゃくちゃピンポイントで自分のニーズに応えられている」と思ってもらえるようにしたり、いくつかの解決シナリオが想像できます。
|
想像シナリオ① 完全に別のインターフェースとして広告動線が用意される 完全に別のインターフェースとして広告導線が用意される場合、AIが生成する回答とは別に「あなたの今回の検索に関連性が高い広告を、AIが独自にまとめました」という別の回答枠がある、といったイメージでしょうか。ちょうどこの記事を執筆している2025年10月には、Googleの従来の検索結果ページでの検索広告の表示形式にアップデートがあり、広告表示領域が「スポンサー広告」として大きめの表題でグループ化され、グループごと非表示にもできるUIに移行しはじめています。広告領域を明確に区別して認識しやすくする変化を加えるこの流れにも近しいシナリオかもしれません。 参考:Google, “We’re improving navigation and introducing a new control for ads on Google Search.”, Google Ads & Commerce Blog, Accessed 24 Oct 2025 ただし、いわゆる「プル型」の検索連動型広告であっても、結局「広告」という手法においては広告主の意図したメッセージを発信できる「コントロール性・プッシュ性」というのが本質的に重要となります。広告の内容自体がAIによって要約・意訳されてしまう場合、広告自体の価値も薄まってしまうリスクも考えられます。そのため、固定文言の設定など、自動生成の中でも制御できる要素をどの程度持てるのか気にしていきたいところです。また、課金形式がどうなるのか、ランディングページから情報が抽出されるのであれば現行の動的検索広告(DSA)と差異が少ないのではないか、など現実的には他にもハードルがありそうです。 |
|
想像シナリオ② 「極めてピンポイントで自分のニーズに応えられている」と思ってもらえる広告への進化 この場合、ユーザーの意図やインテントに合わせた広告表示の精度が、従来以上に求められます。現在のような単純なキーワードマッチではなく、「こういう感じの人とかこういう気持ちの人に広告を配信したいです」というように、ターゲティングの設定がよりオープンな形での指定に進化していくなどの機能進化が付随してくることを期待したいですね。たとえば、広告グループへの「赤坂 居酒屋」というキーワードの設定の形で表現していたものが、「これから赤坂の居酒屋を予約する可能性がある人。赤坂じゃなかったり居酒屋じゃなかったり、まだ具体的な検索行動をしていなくてもいい」など、プロンプトのような形で広告グループにターゲット属性をインプットする形に変わるようなイメージです。 |
また、「AI モード」内で連続して回答を生成する過程で広告が表示されるようになるのであれば、その検索クエリのニュアンスを時系列・文脈的に捉えて広告が最適なタイミングで表示される必要があります。「そこまでのクエリの連なり」として意図を捉えるという点については、現在もプラットフォームが生活者の検索履歴を判断のシグナルに用いていることとあまり大きく変わらない気がしますが、一連の検索プロセスのどこで広告接点を持つべきかという新たな判断軸が生まれることで、「AI モード」における広告体験もまた変わってくるかもしれません。
まとめ
現時点では、日本におけるGoogleの「AI モード」の広告配信はまだスタートしておらず、従来の検索連動型広告の運用におけるトレンドが急に大きく変わることはないでしょう。しかし、この新たなプラットフォームは、生活者の検索行動に影響を与え、将来的には広告の在り方や運用方法にも大きな変化をもたらす可能性を秘めています。今回私が個人の見解であれやこれや考えてみたように「今後どのように変わっていくだろうか?」「どのように変わってほしいだろうか?」を事前に想像しておくことは、いざ大きな転機が訪れた際に重要な糧となるでしょう。新たな兆しや流れをしっかり理解し、その一端をしっかり脳内に繋ぎとめておくことで、今後の検索広告の運用や戦略に活かすことができるはずです。
この記事の著者
森戸 一粋
2015年に株式会社アイレップ(現 Hakuhodo DY ONE)に新卒入社。SEMを中心に飲食・旅行などの大型案件メインで運用型広告のストラテジストとして第一線で活躍。その傍ら、2年目の2016年から早くも運用の専門研修の講師を担当するようになり、社内の運用人材育成を長らく牽引。卓越したスキルと独自の語り口で、社内外どちらからも頼られる運用のプロフェッショナルとして唯一無二の地位を確立している。
2015年に株式会社アイレップ(現 Hakuhodo DY ...