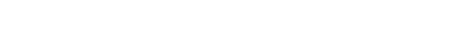昨今、生成AIの進化によって、誰もが手軽に広告を制作・配信できるようになった。一方で、その裏側では著作権侵害や不適切な表現といった「非機能要件」※のリスクが潜んでいる。こうした課題に対し、Hakuhodo DY ONEは「クリエイティブ法務」という新たな仕組みを導入。AI時代に広告会社が提供すべき真の価値とは何か。博報堂DYホールディングスCAIO/内閣府AI戦略専門調査会委員の森正弥氏と、Hakuhodo DY ONE 戦略法務局 クリエイティブ法務 エグゼクティブの藤井正則氏に話を聞いた。
※システムやサービスが「どのような機能を持つか」という機能要件とは別に、そのシステムが「どれくらい性能が高く、安全で、使いやすく、安定しているか」など、品質や性質に関する要件を定義したもの。
写真:
左から)博報堂DYホールディングス CAIO 内閣府AI戦略専門調査会委員 森正弥氏、Hakuhodo DY ONE 戦略法務局 クリエイティブ法務 エグゼクティブ 藤井正則氏
※本記事はAdverTimes.より転載しています。
元記事:https://www.advertimes.com/20251001/article515963/
法務は「ブレーキ役」から挑戦を支える「伴走者」へ
- そもそも「クリエイティブ法務」とは、どのような経緯で誕生したのでしょうか。
藤井:私がアイレップ(現:Hakuhodo DY ONE)に入社した際、クリエイティブの現場と法務との間に大きな距離を感じたのがきっかけです。広告制作の現場はスピードが命ですが、従来の法務は完成したクリエイティブに対して「これはリスクがある」と指摘するだけで、いわば“ブレーキ役”になりがちでした。しかし本来は、表現上のリスクを逆手にとったり、とんちを利かせて上手く利用するからこそクリエイターは本来の力を発揮できるはずです。
加えて、生成AIの普及で新たなリスクが次々と生まれる今、法務のあり方そのものを変える必要があると考えました。法務は「ブレーキをかける人」ではなく、「常に現場に寄り添う伴走者」であるべき。クリエイターやクライアント企業と共に「どうすれば実現できるか」を考え、前に進むための仕組みとして「クリエイティブ法務」を立ち上げたのです。
森:まさに今、AIの進化に世の中の常識や制度のアップデートが追いつかない問題、つまり「ペーシングプロブレム(pacing problem)」が起きています。
例えばAIエージェントによる旅行予約も、チケットなど各購入サイトの利用規約がAIの利用を想定しておらず、取引の有効性が問われる可能性があります。AIが実現する便利な世界に対する期待の裏に、実はさまざまな法的・倫理的課題が潜んでいるわけです。
こうした状況で従来の法務のようにディフェンシブな姿勢に徹すると、すべてを安全策に倒すしかなくなります。藤井さんのようにプロアクティブに、「これは妥当かつ安全だから挑戦してみよう」と判断し、業界の新たなスタンダードを提案していく攻めの視点が、今後は不可欠になると考えています。
- クリエイティブロイヤーが広告制作の段階から関与することで、広告表現はどのように変わるのでしょうか。
藤井:広告表現が「規制で削られるもの」から、「工夫によって活かされるもの」へと変わります。例えば、ある化粧品ブランドの広告で、「よみがえる」という言葉をどうしても使いたいという広告主からの要望がありました。
薬機法などの観点からは誤認につながる恐れがありますが、単にNGを出すのではなく、「※気分が新たになるイメージ表現です」という注釈を加える代替案を提案し、実現に至りました。常にブランドの意図を尊重し、リスクを最小化しながら表現を実現する伴走者でありたいと考えています。
森:グーグルの元副社長マリッサ・メイヤー氏が「Creativity Loves Constraints(創造性は制約を好む)」と語ったように、制約があるほうがクリエイティビティは高まる側面があります。法務が初期段階から関わり、何が「制約」かを明確にすることで、クリエイターはより創造性を発揮できるのではないでしょうか。
藤井:まさにその通りで、最近はクライアント企業への提案前の企画段階での相談が格段に増えました。例えば、「作曲者不詳の楽曲の権利処理はどうすれば?」といった具体的な相談が寄せられます。
こうしたケースではリスクを洗い出し、実現の道筋を一緒に考えることで、後々の手戻りを防ぎ、制作をスムーズに進めることができます。以前は、広告が完成しローンチ前に問題が発覚するというヒリヒリするような場面もありましたが、今ではそうしたケースはほとんどなくなりました。
AIのリスクをAIで防ぐ法務DXの最前線
- AIやAIエージェントの活用が進む今、なぜ「非機能要件」の重要性が高まっているのでしょうか。
森:テクノロジーに対する期待と、それを取り巻く社会の成熟度とのギャップが広がっているからです。画像生成AIが登場した当初は著作権の問題が議論されましたが、AIエージェントが普及すれば、セキュリティや個人情報漏洩など、さらに多様なリスクが生まれます。「便利だから使う」という姿勢だけでは、思わぬリスクを踏み抜いてしまいかねない。だからこそ、非機能要件を熟知したプロフェッショナルとの伴走が重要になると考えています。
藤井:広告の世界では、たった一度の不適切な表現が、ブランドイメージに致命的なダメージを与えかねません。AIのアウトプットに対する安全性、公平性、そして「説明責任」をどう担保するかが不可欠になっていると感じています。
- 現在、社内で運用中のAIリーガル判定ツールについてもお聞かせください。
藤井:Hakuhodo DY ONEでは、AIリーガル判定ツールを独自で開発しています。景表法や薬機法に基づく広告表現をAIで事前チェックし、人間はより付加価値の高い業務に集中できる環境を整えることを目的としています。
本ツールの最大の特徴は、当社が法務とクリエイティブの双方を理解しているからこそ実現できた点にあります。通常、弁護士は法律に、クリエイターは制作に特化していると思います。しかし私には、法律家としての実務経験と日本だけでなく欧米での広告・映像制作の現場で培った経験がありました。さらに、各法令に精通した弁護士との協働や、法律事務所との強固な連携を通じて、ひとりでは到達し得ない、極めて強固な領域を切り開いています。
だからこそ「法律的にどこまで攻められるか」「どの表現ならリスクを回避しつつ前に進められるか」を、実務感覚に基づいて提示することが可能であり、その知見をAIリーガル判定ツールに惜しみなく注ぎ込みました。
リスクを指摘して終わるのではなく、代替案を提示し、前進を支援する。これこそがAIリーガル判定ツールの独自性であり、今後は単なるチェックツールを超えた「代替表現の指揮者」として、広告の未来を支える伴走ツールでありたいと考えています。
森:AIのリスクをAIでチェックする、というのは間違いなく今後の重要なトレンドです。AIが生み出すアウトプット量は爆発的に増え、もはや人間の処理能力を超えている。専門家のノウハウを学習したAIが一次的な防御ラインを築き、そこを突破した高度な案件に人間が集中する。このようなAIとのコラボレーションは、あらゆる業務で必須のフォーメーションになっていきそうですね。
藤井:「クリエイティブ法務」は、広告業界における新たなスタンダードとなりつつあります。Hakuhodo DY ONEは、業界をリードするこの取り組みを通じて、クリエイティブと法務の新しい在り方を提案し続けていきます。
この記事の著者
AdverTimes.
「AdverTimes.(アドバタイムズ、通称アドタイ)」は、株式会社宣伝会議が運営する、企業のマーケティングやメディア、広報、広告クリエイティブなど、コミュニケーション分野を取り巻くニュースや情報を素早く入手することができる広告界の情報プラットフォームです。各分野の専門誌を発行する宣伝会議ならではの取材網を生かし、実務に役立つ情報を提供していきます。ニュース記事のほかには、広告・コミュニケーション分野の第一線で活躍する識者によるコラムや、新たにオンエアされたテレビCM情報をお知らせする「新着CM」などを掲載しています。記事は平日毎日更新します(お盆と年末年始を除く)。
「AdverTimes.(アドバタイムズ、通称アドタイ)」は...