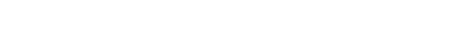本稿では、生成AIと著作権に関する喫緊の課題を、日米欧における法制度の相違点や国際的な議論の現状を踏まえ、解説します。生成AIを活用する企業やクリエイターにとって、生成AIと著作権の問題は、事業展開において無視できない重要なテーマです。創造的な活動の未来を左右するこの重要な論点について、本稿を通じて共に考察を深め、今後のビジネスにおける最適解を見出す一助となれば幸いです。
※サムネイルは生成AIを活用して作成しています
技術革新と社会への適応
生成AIの登場は、単なる技術的進歩にとどまりません。それは、創造行為そのものの定義を根底から揺るがす変革です。人類の歴史を振り返ると、技術の発展は常に社会の受容と対峙しながら、新たな倫理的・法的課題を生み出してきました。印刷技術が宗教改革を促し、写真が美術の概念を揺るがし、映画が舞台芸術の在り方を塗り替えたように、生成AIもまた、創作の領域に不可逆的な変化をもたらしています。
このような、技術の進化は必ずしも無条件に歓迎されるわけではありません。写真の発明に対し、多くの画家が「芸術の死」と嘆き、映画の誕生が「演劇の衰退」を招くと危惧されたことがありました。しかし、そうした懸念は一時的なものでした。やがて写真は絵画とは異なる表現手段として確立され、映画も演劇とは異なる芸術として発展を遂げました。技術革新は、一定の適応期間を経て、より高度なクリエイションの可能性を切り開いてきたのです。
そして今、私たちは新たな転換点に立っています。生成AIの進化により、「創作」という行為はもはや人間だけの専売特許ではなくなりつつあるということです。AIは単なる補助的ツールにとどまらず、時にはクリエイターの右腕となり、時には競争相手としても機能しはじめています。AIによる音楽、アート、文章、映像の生成は、「補助」の域を超え、「制作プロセス」の不可欠な一部になろうとしています。こうした変化は、技術的な視点だけでなく、法的・倫理的な観点からも慎重に捉える必要が出てくるのです。
生成AIと著作権・技術と法の交差点
現在、生成AIの発展に伴い、著作権をめぐる議論が世界中で活発化しています。AIは膨大なデータを学習し、新たなコンテンツを生成しますが、その過程で既存の著作物をどのように扱うかが、著作権法の観点から大きな争点となっています。そもそも著作権法は、人間の創作活動を保護することを目的としており、「創作性」や「オリジナリティ」を重視する法体系のもとで運用されてきました。そのため、AIが生成したコンテンツをどのように位置付けるべきか、従来の枠組みでは十分に整理されていません。現時点で、著作権の観点から特に注目すべき論点は、次に挙げる三つに集約されます。
学習データの適法性:「AIは何処から何を学んでいるのか?」
AIが著作物を学習する行為そのものが、著作権法上の「複製」に該当するのかどうか。この点は、世界的に重要な法的争点となっています。
AIが学習データとして使用するテキスト・画像・音楽などが著作権で保護されている場合、それらを無許可で収集・解析することが「無断複製」と見なされる可能性があります。しかし、この問題に関する解釈は、各国で大きく異なります。
たとえば、米国では「フェアユース(Fair Use)」の概念にもとづき、一定の条件下で著作物の利用が認められる可能性があります。一方、EUでは、AIの学習データは適法に取得されたものでなければならないとする規制が強化されており、無許可でのデータ収集が問題視されるケースが増えています。 日本でも、著作権者の許可を得ずに著作物を学習データとして利用することが、著作権侵害に当たるかどうかの議論が進められています。
一方で、AI開発企業の中には「AIは作品そのものではなく、パターンや統計的特徴を学習しているに過ぎないため、著作権侵害には当たらない」と主張する意見もあります。しかし、この理論はまだ法的に確立されておらず、今後の判例や法改正の動向によっては、解釈が大きく変わる可能性があります。
生成物の類似性:「AIが生んだものは盗作なのか?」
AIが生成したコンテンツが既存の著作物とどの程度類似しているかは、著作権侵害をめぐる大きなリスクとなります。特に問題となるのは、以下のようなケースです
|
これらの問題は、特に画像生成AIや音楽生成AIの分野で顕著に見られます。たとえば、あるAIが「特定のアーティストの作風を模倣する」ことを目的に学習し、その結果、既存の著作物と酷似した作品を生成した場合、それは「二次的著作物」として著作権侵害に問われる可能性があります。また、AIは統計的処理を通じて最適な出力をおこないますが、時には「偶然にも既存の作品と極めて類似したもの」を生成することがあります。この場合、意図的な盗作ではなくとも、著作権侵害と判断されるリスクは否定できません。
たとえば、AIが特定のアニメキャラクターや企業ロゴを生成した場合、使用者が意図していなくても、著作権者や商標権者からクレームを受ける可能性があります。そのため、多くの企業は、AIによる生成物の「著作権クリアランス」(他者の著作権を侵害していないかの調査)をおこなう必要に迫られています。
著作権の帰属問題:「AIが作った成果物は誰のもの?」
ところで、AIが生成したコンテンツの著作権は、一体誰に帰属するのでしょうか。
現在の著作権法では、「創作的寄与をおこなった人間」に著作権を付与するのが原則とされています。そのため、AI単独で生成したコンテンツには著作権が認められないというのが、米国著作権局(USCO)や日本の文化庁の基本的な立場です。
しかし、問題となるのは「AIを操作する人間」の関与度によって、著作権の扱いが変わる点です。たとえば、
|
この問題に関して、EUでは「人間の創作意図が介在する限り、著作権保護の対象となり得る」との見解が示されており、各国で対応が分かれています。
▼国際的な見解を整理してみると
|
地域 |
AI生成物の著作権の扱い |
|
米国(USCO) |
「AIが完全に自動生成したコンテンツには著作権を認めない」 |
|
EU |
「人間の創作意図が介在する限り、著作権保護の対象になり得る」 |
|
日本(文化庁) |
「AIが自律的に生成した場合は著作権なし」 だが、「人間が関与した場合はケースバイケース」 |
この議論の中で、日本では「プロンプト」の重要性が指摘されています。つまり、AIをどのように操作したか、そしてどの程度人間が創作に関与したかが、著作権の帰属を決定する要素になりつつあります。たとえば、単に「風景画を描いて」と指示しただけでは、創作性は低いと見なされます。しかし、「特定の構図・配色・要素を細かく指定し、AIが生み出した複数の候補から選び、修正を加えた場合」は、著作権が認められる可能性があります。
2025年6月時点での結論:国際的な統一見解はまだ確立されていない
著作権法はもともと、人間による創作物を保護するための制度です。しかし、AIという「非人間的な創作者」の登場により、私たちは根本的な再考を迫られています。現時点では、国際的な統一見解はなく、各国の法制度によって対応が異なるのが実情です。
この分野では、今後の判例や法改正が重要な役割を果たしていくと考えられます。たとえば、欧州ではAIの著作権を整理するための新たな指針の策定が進められており、米国でも著作権局が新たな方針を打ち出す可能性があります。
いずれにせよ、生成AIの普及が進む中で、企業やクリエイターは「AIの活用方法」「学習データの適法性」「生成物の権利処理」について、より慎重な対応を求められるようになるでしょう。また、AIの台頭は単なる技術的進歩ではなく、法と倫理の枠組みをどのように構築していくかが、生成AIと共存するための重要な課題となります。
▼関連動画
この記事の著者
藤井 正則
フランス生まれ。欧州のメジャー映画配給会社に13年間在籍し、映画製作・配給やCM制作の現場において、渉外業務と契約法務の両面を担当。複数言語環境および異なる商習慣のもと、フランス共和国弁護士(兼 欧州弁護士 / 仏英・仏独)として活動し、常に最適解を追求する「クリエイティブ専門弁護士」としての経験を積む。 2019年より都内法律事務所にて外国法弁護士として勤務し、2022年に旧アイレップ(現 株式会社Hakuhodo DY ONE)に法務局の責任者として入社。2023年10月より「クリエイティブ法務」サービスを立ち上げ、広告・表現内容に関する全件審査を、法律とクリエイティブの両視点から一気通貫で対応中。 現在は、日本語・英語・中国語の各種契約書(米国各州法・中国法・英国法ほか)にも対応し、多言語・多法域にわたる広告・契約実務を担う法務スペシャリストとして活動。
フランス生まれ。欧州のメジャー映画配給会社に13年間在籍し、...