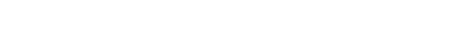前編では、生成AIと著作権をテーマに、技術革新がもたらす法的・倫理的課題と、それに対する国際的な動向を概観しました。生成AIはまさに進化の途上にあり、法整備や社会通念も変化していく過渡期にあります。だからこそ、継続的な情報収集と議論が不可欠です。今回は、この現状を踏まえたHakuhodo DY ONE独自の生成AIを用いたクリエイティブ制作の在り方について紹介します。既存の枠組みにとらわれず、新たな可能性を模索する私たちの取り組みを、ぜひご一読ください。
▼関連記事
※サムネイルは生成AIを活用して作成しています
「攻めるクリエイティブ」と「守る法務」を。
このような現状から、現在のクリエイティブでは、表現の自由と法規制のバランスを取ることが、これまで以上に重要な課題となっています。特に、AIを活用した広告やプロモーション、医薬品・健康食品のマーケティングにおいては、企業がコンプライアンスを維持しながらも、攻めたクリエイティブを展開するために、常に倫理観にも配慮する必要があります。
こうしたAIの黎明期を迎えたいま、Hakuhodo DY ONEは「クリエイティブ法務」という専門領域を2023年10月にスタートさせ、広告・マーケティングの最前線と法務をつなぐ独自の審査体制を築いてきました。その一端をご紹介します。
そのコンセプトにあるのは、
「ルールを守る」だけでなく、「ルールの中で攻める」クリエイティブへ
単に法規制を遵守するだけでは、強いクリエイティブが生まれることはありません。重要なのは、法的リスクを抑え、ブランド価値を最大化する表現を実現することです。そのためには、映画・テレビ・CM・興行など、あらゆるクリエイティブ領域での制作現場で培ったノウハウと実務経験、それらの仕事を進める上で必要な法的要素への深い理解と造詣が不可欠です。
さらに、広告やコンテンツがSNSを通じてグローバルに展開される現代においては、各国の法的要素や規制を理解し、それぞれの市場に適応する視点も求められます。国や地域ごとの法律の違いを踏まえたリーガルチェックができなければ、クリエイティブの安全性を担保することはできません。 Hakuhodo DY ONEのクリエイティブ法務は、制作現場で蓄積された知見と国内外の法的知識を融合させ、グローバルな視点で最適なサポートを提供します。
そこで、Hakuhodo DY ONEのクリエイティブ法務は、以下の3つのアプローチでクライアントの皆様を支援することをお約束します。
国内外の法規制を網羅した高度なリーガルチェック
クリエイティブ法務では、日本国内の薬事法・景品表示法・医師法に加え、米国のAMA(American Medical Association)や欧州を含む海外市場の広告規制にも対応しています。世界各国で商品やサービスを展開する際には、各市場特有の法規制を理解し、適切なリーガルチェックをおこなうことが不可欠です。
たとえば、EUにおける広告規制の一般法には、1984年9月に施行された誤認広告に関する指令(84/450/EEC)や、その改訂版である比較広告に関する指令(97/55/EC)があります。 また、テレビ放送に関する規制としてテレビ放送指令(97/36/EEC)が適用されており、テレビ通販に関する規制も整備されています。さらに、タバコ広告の制限、食品のラベル・包装および広告に関する規制、化粧品の表示ルールなど、多岐にわたる指令が存在し、現在のEU広告規制の基盤を形成しています。
クリエイティブ法務は、こうした国内外の規制を深く理解し、実務に適用するノウハウを有しています。特に、厳格なEUの広告規制にも対応できる体制を整えているため、海外市場への展開を検討するクライアント企業の皆様にも、安心してご相談いただけます。
たとえば、EUでは2026年から環境広告に関する規制が強化される予定であり、サステナブルやゼロカーボンといった表現の使用には、より厳格なルールが求められます。 具体的には、以下の3点が禁止されます。
|
このように、各国の法規制を正しく理解し、適切な広告表現を用いることは、グローバル展開においてますます重要になっています。 クリエイティブ法務では、広告表現の審査に加え、知的財産やAI活用に関するリスク評価も包括的に実施し、ビジネスを法的リスクから守る体制を整えています。最新の規制動向を常に注視し、各市場に応じた適切なリーガルチェックを提供することで、グローバル展開をサポートしてまいります。
実態に即した柔軟な代替案の提案
法的に「NG」と判断するだけではなく、「どうすれば表現が可能になるのか?」を現場と一緒に考え、リスクを回避しながら法律の枠組みの中で可能な限り攻めた表現を提案することを重視しています。 具体的には、クリエイティブ制作現場とクリエイティブ法務が密接に連携し、チャットツールを活用した迅速でフランクな相談体制を整えています。これにより、常にスピーディーなフィードバックを提供できる環境を構築しています。現在の審査は、人力による丁寧なチェックを基本としていますが、審査範囲やページ数などの分量によって対応スピードに影響が出る課題もあるため、さらなる業務効率化のためにAIを活用した審査プロセスの導入も検討しています。
今後は、AIによる自動化と人力による精査を組み合わせたハイブリッド型の審査体制の構築を目指し、定型的な審査をAIで効率化しつつ、専門的な判断が求められる案件については人の目で確認精度を高める方針です。これにより、より迅速かつ精密な審査を実現し、クリエイティブの 自由度を保ちながら法的リスクを最小限に抑えていきます。
AI利用ガイドラインを策定:透明性と信頼の確保
生成AIの普及が進む中、著作権や倫理的課題への対応は、より慎重かつ戦略的なものになっています。クリエイティブ法務では、AI生成コンテンツに関する知的財産権のリスクや倫理的な問題を精査し、クリエイティブ制作現場が安心して活用できるAI利用におけるガイドラインを当社のAI戦略開発室と共同で策定しています。
また、米国・欧州の最新判例や規制動向を継続的にリサーチし、クライアント企業が広告素材をグローバル展開する際に生じるリスクを回避するためのサポートもおこなっています。特に、著作権や商標権のクリアランス手続きを含め、各国の法規制を踏まえた適切な対応策を提案し、安全かつ効果的な生成AIの活用を支援しています。また、クライアント企業へ納める成果物に対し、許可なくAIを使用することは一切なく、納品成果物の制作プロセスにおいて、以下の3つのルールを厳格に運用しています。
|
これらのルールを基に、透明性を担保しながら、クリエイティブの現場を支援していきます。
また、クライアント企業の皆様が生成AIを用いたクリエイティブを取り扱う場合に役立つガイドラインの提供もしていますので、社内での生成AI活用についてのルール作りにお悩みの方はぜひ当社にお声がけください。
クリエイティブと法務の両立を実現するパートナーへ
クリエイティブと法務の両立は容易ではありません。しかし、それを可能にするのがHakuhodo DY ONEの「クリエイティブ法務」です。それは社内インフラの単なる「チェック機能」ではなく、法的リスクを適切に管理しながら、最大限にクリエイティブの可能性を引き出す戦略パートナーとして、クライアント企業のビジネスを前進させることを目指しています。
「どうすれば、より自由に、より戦略的に攻めることができるのか?」
その答えを、法務とクリエイティブの両面から共に考え、最適なソリューションを提供していきます。
この記事の著者
藤井 正則
フランス生まれ。欧州のメジャー映画配給会社に13年間在籍し、映画製作・配給やCM制作の現場において、渉外業務と契約法務の両面を担当。複数言語環境および異なる商習慣のもと、フランス共和国弁護士(兼 欧州弁護士 / 仏英・仏独)として活動し、常に最適解を追求する「クリエイティブ専門弁護士」としての経験を積む。 2019年より都内法律事務所にて外国法弁護士として勤務し、2022年に旧アイレップ(現 株式会社Hakuhodo DY ONE)に法務局の責任者として入社。2023年10月より「クリエイティブ法務」サービスを立ち上げ、広告・表現内容に関する全件審査を、法律とクリエイティブの両視点から一気通貫で対応中。 現在は、日本語・英語・中国語の各種契約書(米国各州法・中国法・英国法ほか)にも対応し、多言語・多法域にわたる広告・契約実務を担う法務スペシャリストとして活動。
フランス生まれ。欧州のメジャー映画配給会社に13年間在籍し、...