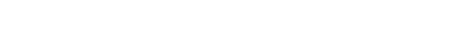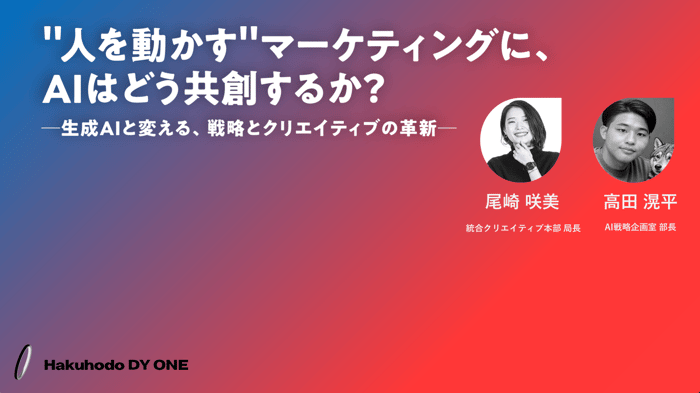
2025年6月に開催された、Eight(Sansan)主催「Eight EXPO 第4回 営業マーケDX 比較・導入展」において、「“人を動かす”マーケティングにAIはどう共創するか?生成AIと変える、戦略とクリエイティブの革新」をテーマとした講演に、当社から統合クリエイティブ推進局 局長の尾崎とAI戦略開発室 部長の高田が登壇しました。本記事では、Hakuhodo DY ONEが提唱する革新的なクリエイティブ戦略と生成AI活用の最前線について、本講演でお話した内容をもとに詳しくお伝えします。
デジタル広告の変遷と現在の課題
- まず、現在のデジタル広告環境について教えてください。
尾崎:デジタル広告の変遷を振り返ると、2000年代は純広告やマス広告が主流で、デジタルにおいては、大手ポータルサイトのトップページなどが主要な広告掲載面でした。当時はまだ、現在のような多様なコミュニケーションプラットフォームや短尺動画共有サービスは存在していませんでした。
その後、ソーシャルメディアの普及や、検索エンジンを基盤とする広告プラットフォームが台頭。より詳細なターゲティングが可能になり、運用型広告が主流となりました。そして現在、AIによる自動化が、広告運用とクリエイティブ制作の両面で急速に進展しています。
特に重要なのは、媒体側の配信アルゴリズムや最適化がAIの発達により高度化したことです。私が広告運用の業務を担当し始めた頃は、広告配信の管理画面に張り付いて、日々の数字の動きを自分の目で見て確認しながら手動で入札調整していました。今ではその多くをAIに任せられるようになりました。
その結果、AIによる広告運用の自動化が進み、成果を左右する要因としてクリエイティブの重要性が相対的に増しています。そのため、クライアント企業からもクリエイティブでの成果創出をより強く求められるようになっています。

メディア環境の劇的な変化が運用クリエイティブの重要性を押し上げる
- デジタル広告におけるクリエイティブの重要性について詳しく聞かせてください。
尾崎:デジタル広告でクリエイティブによる成果を創出するためには、二つの重要なファクターがあります。一つは生産スピードと量産体制、もう一つはブランドの価値創造です。
運用型広告では、媒体入稿から成果分析、ネクストアクションの決定、クリエイティブ制作、再配信という一連のPDCAサイクルを約二週間で回すスピード感が求められます。
なぜこれほどのスピードが必要かというと、主要メディアの最適化AIアルゴリズムを効果的に活用するためには相当な本数のクリエイティブが必要で、さらに継続配信により広告の摩耗も起こるからです。つまり、デジタル広告ではスピードと物量の両方が求められるのです。

高速PDCAにより勝ち筋が見えてくるため、短期間で成果を実現するにはクリエイティブの勝ちパターンを明らかにして量産することが成果創出の鍵となります。ただし、これを突き詰めていくとクリエイティブの均質化が進んでしまいます。獲得型広告では、セールや価格などの具体的なスペックを訴求することが効きやすいのは皆さんもご存知かと思いますが、それだけではユーザーの心に響く長期的な関係構築は難しいという課題も生まれます。
Call-to-Action(CTA)のこれから
- CTAクリエイティブの現状と課題について教えてください。
高田:Call-to-Action、いわゆるCTAクリエイティブとは、皆さんがよく目にするバナー広告のことです。生活者が今すぐ行動に移すための呼びかけ、成果直結の後押しをするクリエイティブコミュニケーションです。
たとえば、「今なら5,000円プレゼント」「バレない状態でクマ取りができます」「年収700万円から960万円にキャリアアップ」といった直接的なオファーをするのがCTAクリエイティブです。
CTAクリエイティブの均質化が課題として挙げられますが、私たちはこれを逆に捉え直しています。均質化したということは、生成AIで高速化できる領域だということです。
文脈理解型画像生成モデルが制作現場にもたらした革命
- 生成AIの進化について具体的に教えてください。
高田:画像生成AIの変遷を振り返ると、2022年頃からDALL-E 2、Stable Diffusion、Midjourneyなどが登場しました。当初は「画像が出せるんだね」程度の感覚でしたが、品質は徐々に向上していきました。
しかし、2025年3月26日、私たちの常識は大きく書き換えられました。OpenAIがChatGPT内での画像生成機能をリリース したのです。これにより、より高度な文脈理解と自然言語処理能力を備えた画像生成モデルが登場しました。従来の画像生成AIのように、複雑で長いプロンプトを詳細に記述する必要がなくなり、ごく自然な言葉で意図を伝えるだけで、適切な画像を生成してくれるようになったのです。
we are launching a new thing today—images in chatgpt!
— Sam Altman (@sama) March 25, 2025
two things to say about it:
1. it's an incredible technology/product. i remember seeing some of the first images come out of this model and having a hard time they were really made by AI. we think people will love it, and we…
出典:Sam Altman ,”We are just launching a new thing today...”, X, posted 26 Mar 2025, https://x.com/sama/status/1904598788687487422
※OpenAIのCEOサム・アルトマン氏が自身のX公式アカウントでChatGPT内における画像生成機能のリリースを発表
リリース後、私は手元にあった無水エタノールのボトルを撮影し、「この商品を使ったバナー広告を作って」と指示しました。すると、たったそれだけの指示で、バナーらしきものが生成されました。「もっとダイナミックなレイアウトを提案して」と言えば集中線がデザインに加わり、「縦型にリサイズして」と言えばすぐに対応してくれました。これが一言のプロンプトでできてしまう時代が突然やってきたのです。

翌日には、クライアント企業の広告バナーを一定品質で量産できるようになっていました。
大量制作とAI予測システムの戦略的組み合わせ
- 制作フローはどのように変化しましたか?
高田:従来は提案準備に2週間、デザイン制作に1週間、サイズ展開に1週間と、配信まで約1ヶ月かかっていました。しかし現在は、「生成AIに依頼した瞬間にバナーが生成される」という世界が現実になったことで、1週間で提案準備から配信まで完了できるようになりました。

重要なのは、制作コストが大幅に下がったことで「まず制作し、配信してみよう」という考え方が可能になった点です。成果が期待できるクリエイティブは人間がブラッシュアップし、意図に沿わないクリエイティブはサンクコストを気にせず不採用と判断できます。
社内検証の結果、2週間で700本のバナーが生成されました。さらに、クリエイティブ制作を実行したほとんどが、非クリエイター人材によるものだったことが分かりました。これまでクリエイティブ職の人間しかできなかった提案を、誰もが「今このクリエイティブが必要だ」と感じた瞬間に実現できるようになったのです。
私たちは博報堂DYグループ独自開発の成果予測AI「CREATIVE BLOOM」を活用しています。これはクリエイティブ入稿時の市場平均に対するインプレッションやクリック率の予測スコアを偏差値形式で出力するシステムです。

今後の運用型広告は、効率よく広告を掲出して成果を最大化することを目的に、その達成手段として「大量制作」「スコア予測AI」「最適化配信」を組み合わせるアプローチが重要になります。大量制作は目的ではなくあくまでプロセスであり、生成AIを活用して網羅的にクリエイティブを迅速に生成するのが合理的です。その上で、予測AIで偏差値40以下を足切りし、残りを広く配信する。最適化配信によって成果の良いクリエイティブに配信が自然に集中した段階で、人間がその要素を分析し、さらに質の高いクリエイティブに磨き上げる──この検証と改善のサイクルこそが、効率と成果の両立を実現します。

実際の事例では、大量制作と最適化配信により、1ヶ月でコンバージョン(以下、CV)が12%純増しました。さらに、成果の良かったクリエイティブの要素を分析して人間が作り直したクリエイティブは、もとのクリエイティブと比較して5倍のCVを獲得するという大きな成果をあげました。
Hakuhodo DY ONEが提唱するクリエイティブメソッド「Attention-to-Action」
- ATAについて詳しく教えてください。
尾崎:Attention-to-Action(以下、ATA)は、私たちが再定義したクリエイティブメソッドです。まず問いかけたいのは「広告で言いたいことだけをただ言っていませんか?」ということです。
近年、メディア環境の変化により、ユーザーのデジタル広告に対する視聴態度も大きく変わっています。YouTubeを見るときにスキップボタンに集中してしまうのは、私たち広告業界の人間でも同じです。
SNSネイティブな世代が生まれ、広告に対してもネイティブになり、情報を選び取る力が向上しています。言いたいことを言っているだけの広告は、ユーザーに無視されてしまいます。だからこそ、言いたいことを受け手が聞きたいように伝える広告がより重要になっています。
ATAは、生活者が自発的に行動を起こすための興味や関心を引き起こすクリエイティブメソッドです。ユーザーの行動の背後にある感情や心理に働きかける情報を提示することで、生活者に新しい行動を作り出してもらうことを目的としています。
感情トリガーによる自発的行動の創出
- CTAとATAの使い分けについて教えてください。
尾崎:人間の心には三つのフォルダがあると考えています。メディアで情報を見た時、脳は「そのサービスを利用したい」「どちらでもいい」「利用しない」のいずれかに振り分けます。
「利用したい」と思った人たちには、行動を移すような呼びかけ、成果に直結するコミュニケーション、つまりCTAが効果的です。
一方、「どちらでもいい」人たち、まだモチベーションが顕在化していない人たちには、自発的に行動を起こすための興味・関心を引き起こすATA的なコミュニケーションが効果的です。
具体例を挙げると、美容クリニックのクマ取り施術に関する広告で、CTAなら「バレないクマ取り、すぐにできて○○円」と直接的に訴求します。ATAなら「左と右、印象が違うのはどこでしょう?」とクイズ形式にして、人間が一瞬考えてしまう癖を利用します。
転職サイトに関する広告でも、CTAなら「年収700万円アップ」と具体的メリットを示します。一方でATAなら「年収1,024万円を目指す」という、理系人材が美しいと感じやすい数字(2の10乗)を使って「理系職を理解している転職サイトだな」と感じさせます。

生成AIがもたらす表現力の無限拡張
- ATAでの生成AI活用について教えてください。
尾崎:お見せした事例は、全てのビジュアルに生成AIを使用しています。制作スピードの向上と、アテンションのある絵作りの両方で生成AIは非常に有効です。
イラストや3DCGでは、以前は同じキャラクターで別のポーズや表情を作るのが困難でしたが、今はさまざまなパターンを簡単に作れるようになりました。人物生成でも、実在しない人物を自然に動かすことが撮影なしで可能になっています。

ナレーションやBGMもAIで作成できるようになりました。従来は獲得型広告でスピードが求められるのに、ナレーション会社での収録が必要でしたが、それも解消されました。
さらに、2024年には博報堂DYグループの社内ベンチャープログラムを通じて、当社のクリエイティブメンバーが中心となり、AI駆動型クリエイティブ制作会社「ZETTAI WORKS」※を立ち上げました。より高度なAI技術を使った絵作りが可能で、Yogiboのコンテストで最優秀賞を獲得したAI動画事例や、ショートアニメ制作なども手がけています。
※ZETTAI WORKSは、博報堂DYグループのグローバル社内ベンチャープログラム「Ventures of Creativity」による初年度のビジネスコンテストで選出されたビジネスプランです。起案者3名(佐藤、小野、伊豆)はいずれもHakuhodo DY ONEの出身であり、博報堂DYホールディングスとVoC社が共同出資の上、同社を設立。
これにより制作期間、スピード、工数が大幅に削減され、アイデアを実現するためのクリエイティブの選択肢が格段に広がりました。さまざまな制約からチョイスできなかった表現が選び取れるようになったのは、クリエイターとして視野が広がり非常に嬉しいことです。
現場の実践的課題と解決への道筋
- 生成AI活用における著作権の考え方について教えてください。
尾崎:まず、利用するツール選択についてです。生成AIのツールは何でも使って良いわけではありません。当社では、社外のクリエイターが制作した既存の作品を学習したAIツールなど、リスクの高いものは絶対に使用しません。ツールの商用利用条件については、クリエイティブを専門とする法務のエキスパートチームとAI戦略のエキスパートチームが連携して調査したうえで選択しています。
生成された出力物についても、細心の注意を払っています。似たようなものが世の中に存在しないか、独自のチェックツールを使って確認しています。最も重要なのは人の目による最終確認です。
法律上、著作権侵害は依拠性と類似性で判断されます。しかし、それ以上に、生活者の倫理的な感情を害して炎上するリスクの方が、ブランドを守る観点では重要だと考えています。私たちは、著作権を守るだけでなく、倫理的に問題ないかを判断したうえで世に出すフローを徹底しています。

- デザイナーの役割の変化について教えてください。
尾崎:当社には約200人のデザイナーがいますが、彼らもAIを使って表現の幅を広げています。最初はAIに対する危機感や恐怖心もありましたが、実際にツールを使ってみると表現の幅が広がり、デザインの質が向上したという声を多く聞きます。
先ほど高田がお話しした事例が象徴的です。AIを使った大量制作で12%の純増を達成し、さらに人間がその良い要素を分析してブラッシュアップしたクリエイティブは5倍の成果を上げました。この差に人間の価値があると考えています。
AIがこれまでやらなければならなかった作業を代行してくれるようになったことで、やれなかったことにチャレンジできる余白が生まれました。今回のATAのような新しいメソッドもその中から生まれています。
デザイナーも、トレンドの細かいニュアンスを表現するGen Z世代(ジェンジー世代:Z世代)向けクリエイティブの創出など、AIよりも人間が強みを発揮できる領域はまだたくさんあります。AIからアイデアを得て大量にクリエイティブを生成したうえで、人間が「キュンとするか」「ドキドキするか」「ワクワクするか」といった感情的な部分を微調整していくクリエイティブは、依然として非常に強力です。
さいごに
尾崎:最後にお伝えしたいのは、生活者の行動を後押しするCTA(データとAIを中心とした大量生成クリエイティブ)と、生活者の行動を引き起こすATA(アイデアを中心とした企画型クリエイティブ)は、どちらか一方だけでは不十分だということです。
両輪を回していくことが、これからの時代の重要なクリエイティブストラテジーであり、これが今日私たちがお伝えしたかった核心です。デジタル広告クリエイティブは確実に転換期を迎えており、運用型広告の新たな突破口として、CTAとATAの戦略的な組み合わせが不可欠となるでしょう。
この記事の著者
DIGIFUL編集部
「DIGIFUL(デジフル)」は、株式会社Hakuhodo DY ONEが運営する「デジタル時代におけるマーケティング」をテーマにした、企業で活躍するマーケティング担当者のためのメディアです。
当社がこれまでに得たデータや経験から、具体的事例・将来展望・業界の最新注目ニュースなどについて情報を発信しています。ニュースやコラムだけでなく、日常業務や将来のマーケティング施策を考えるときに役立つダウンロード資料や、動画で学べるウェビナーコンテンツも随時追加していきます。
デジタルマーケティングの最新情報や知見を得るための信頼できる情報源の1つとしてお役立てください。
「DIGIFUL(デジフル)」は、株式会社Hakuhodo ...
尾崎 咲美
2015年にアイレップ(現Hakuhodo DY ONE)に入社。4年間ストラテジストとして運用コンサルティングで大型案件を運用後、現在は獲得領域のクリエイティブプランニングとマネジメントに従事。媒体と運用を熟知したロジカルなクリエイティブ分析とPDCAが強み。現在は獲得領域における新しいクリエイティブ表現とミドルファネル開拓を推進中。テクノロジー部門を兼任しており、クリエイティブAI企画開発やクリエイティブのシステム開発にも携わる。
2015年にアイレップ(現Hakuhodo DY ONE)に...
高田 滉平
2020年にアイレップ(現Hakuhodo DY ONE)に入社。獲得クリエイティブのディレクターとして、多数の大型案件でクリエイティブPDCAを支援。現在は生成AIを活用したクリエイティブ制作フローの改革を推進。現場ニーズへの深い理解を強みに、クリエイティブの大量生産やミドルファネル開拓に向けたプロダクト開発をリードしている。
2020年にアイレップ(現Hakuhodo DY ONE)に...