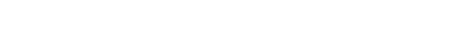2025年は「AIエージェント元年」として注目されており、マーケティング業界においても大きな話題となっています。Hakuhodo DY ONEでは、この潮流が本格化する前の2024年からいち早くAIエージェントに取り組みはじめ、新しい事例を創出してきました。プロジェクトを率いたパフォーマンスAI戦略室室長の山口俊亮は、AIエージェントには従来のAIとは異なる課題があったといいます。本稿では、AIエージェントが導く次世代のマーケティングとそこに待ち構える課題に迫ります。
※本記事の一部は、生成AIツール「Dify」を活用して生成されました。なお、最終的な記事内容の確認・編集はDIGIFUL編集部がおこなっております。
「深く考えるAI」の登場
- AIエージェントがマーケティング業界に与える影響とはどのようなものだと考えていますか。
山口: AIエージェントとは、複雑なマルチステップのワークフローを実行し、特定の課題や作業を半自動的におこなうプログラムのことです。
AIエージェントの登場により、これまで自動化が難しかった多様で複雑なケースを解決することができると考えています。特に注目したいのは、2024年末から登場しはじめた「深く考えるAI」。「深く考えるAI」は私の造語で、じっくりと時間をかけ、さまざまな観点を考慮し、深い答えを出すLLMやAIエージェントのことを指します。
2024年時点での社会におけるLLMへの期待は、ユーザーの求める答えを素早く出すことにありました。しかし最近のLLMはひとつの回答に5~7分かかることがありますし、AIエージェントがひとつのタスクを処理するのに20~30分を要することも珍しくありません。これは一見、効率が悪いように思えるかもしれません。しかし、人間が考えるよりもはるかに多くの情報を処理し、多角的な視点から解を導き出すことができるのです。
さらに興味深いのは、AIエージェントが架空や空想の領域にも踏み込める可能性があることです。「架空」や「空想」というと、これまでは人間が得意な領域だと考えられてきました。しかし実用的なAIエージェントが開発されれば、現実の環境に即しつつ、架空の討論を深めることができるようになるでしょう。

それは喜ばしいことであるのと同時に、これまでのAIとは異なる姿勢でAIに向き合わなければいけない時代が訪れたということでもあります。架空上で思考を深められるということは、人間の思考力がAIに追い付かない時代が迫っているということでもあるからです。
▼関連記事
AIエージェントに取り組む中でぶつかった壁
- Hakuhodo DY ONEでは2024年からマーケティングにおけるAIエージェント活用に取り組みはじめてきました。その中で気づいた「今の時代に求められるAIとの向き合い方」について教えてください。
山口:昨年、ある広告主のリブランディングに伴い、新しいロゴを考案する必要がありました。そこで当社では「社長や取締役など、クライアント企業の経営者を模したAIモデルが討議をおこない、解決策を導き出す」というAIエージェントを活用することにしました。このAIエージェントを使って、新しいロゴに込めたいメッセージについての討論をAI上の経営者に実施してもらい、その討論結果をロゴ制作のプロセスに活用したのです。
このAIエージェントでは、まず討論が成立するようにAIエージェント上でファシリテーター役を用意し、議論の誘導やAI上の経営者たちへの質問の投げかけをおこなわせました。また、AIエージェント操作者があらかじめ指定した議論の到達点にたどり着いたかを確認する機能も備え、それまでにおこなわれた議論の過不足をAIが判断できるようにしました。さらに、AI上の経営者たちが本物の彼ららしく振る舞えるよう、実際の経営者の発言データを参照して回答を生成するようにしたのです。

多忙な経営者同士で議論していただくのは、スケジュールの調整上、かなり難しいことです。しかしこのシステムを使うことで、本来であれば1回の議論でも相当な時間、経営者を拘束しなければいけないところを、AIエージェント上で架空の討論を100回近く実施することができました。これにより、多様なシナリオを検討することが可能になったのです。
ところが、その過程で大きな課題に直面しました。
- どのような壁にぶつかったのでしょうか。
山口:AIエージェント上で実施された経営者同士の討論は非常に視座が高く、特に若手メンバーはその内容を解釈しきれないという事態に陥ったのです。しかも100回近くの討論を実施しましたから、出力されたテキストも膨大で、読むスピードが追い付きませんでした。AIの思考力が人間を超えつつある証左ともいえるでしょう。
そこでAIエージェントから出力された討論のテキストを、そのまま別の画像生成AIに流し込み、ロゴとして出力させることにしました。つまり、人間には理解しづらい高度な討論内容を、別のAIを使って視覚化したのです。結果として出力されたロゴは、人間には思いつかないような斬新なものでした。それは広告主からも高く評価されました。

2025年、AIの活用方法が変わる
- 従来のAIと同じ姿勢でAIエージェントに向き合うと、うまく活用できない可能性があるということですね。
山口: こうした事例を通して、AIエージェントの活用方法は、従来のAI活用と大きく異なる可能性が見えてきました。2024年時点では、多くの人がAIを思考の補佐役として活用していました。つまり、人間が思考プロセスを組み立て、その過程で壁打ち相手としてAIにサポートしてもらうという使い方です。しかし、AIエージェントの登場によって、この使用方法が変わりつつあります。
2025年はAIエージェントがブームになると言われていますが、こうした「深く考えるAI」が進化していくと、AIのアウトプットに人間の解釈がついていけなくなる可能性があります。また、AIの処理スピードは人間よりも速いため、大量のアウトプットを人間が解釈しきれなくなる、いわゆる処理オーバーの状態に陥る恐れがあります。
AIエージェントの大きな利点は、マルチステップのワークフローを組むことで、人間の指示を最小限に抑えられることです。人間は思考プロセスの途中で出された未完成のアイディアよりも、完成されたアイディアの方が理解しやすい傾向があります。たとえAIエージェントが途中で出した大量のアウトプットを人間が解釈しきれなくても、AIエージェントに最終的な完成物まで一気に出力させることで、人間が感性で判断できるレベルにもっていくことができるのです。先ほどご紹介した経営者討論AIエージェントの事例においても、思考プロセス途中におけるAIエージェントのアウトプットは、人間には解釈しにくい内容を多く含んでいました。しかし、それをロゴという完成形で視覚化することで、人間が理解できるものに変換することができました。

しかもAIエージェントから出力された完成物においては思考プロセスを遡って確認できます。シングルステップでAIを活用すると、ステップごとに人間の解釈を経るため、時に論理の飛躍が生じることがあります。一方、AIエージェントの出力した完成物は、人間が感性で判断できると同時に、その裏側にしっかりとしたロジックがあり、感性による判断に論理的な説明を付けることができるのです。
AIエージェントならではの創造性とは?
- AIエージェント活用のカギは『完成形にまでもっていく』というところにあるのですね。AIエージェントが出力した完成形と人間が作り出す完成形との違いはありますか。
山口:人間の解釈を経ないで得られたアウトプットは、人間とは異なる創造性をはらんでいます。人間の常識や慣習にとらわれないことこそ、AIエージェントが生み出す最大の創造性といえるでしょう。
今回の事例において、経営者討論AIエージェントの出力データをもとにロゴを生成させたところ、3Dのロゴや色のグラデーションがついたロゴが出力されました。こうしたロゴは印刷時や白黒表示時に使い勝手が悪いため、通常、人間のクリエイターが避ける表現方法です。しかし、AIエージェントはそういった慣習を知らないため、自由な発想でロゴを生み出せました。今回は幸いにも、広告主がデジタル関連事業を展開していたこともあり、3Dロゴやグラデーション付きのロゴはむしろ新しいブランドイメージを表現するものとして高く評価されました。
今回の事例では、経営者の討論とロゴ生成で使用するAIを分け、ふたつのステップを踏みました。それはある程度、人間がAIを制御する必要があると考えていたからです。しかし、今後はあえて人間の指示を介さず、AIエージェントにより多くのステップを任せる方が、AIにしか出せない優れたアウトプットを生み出せると考えています。AIエージェントを使ったマーケティングのカギは「完成形にまでもっていく」ことですが、それはいいかえると、人間の先入観を排除し、AIの創造性を最大限に引き出すということなのです。

AIの創造性を生かすために人間に求められること
- 今後のAIを活用していく中で、人間が意識的に身につけなければいけないことはありますか。
山口:AIエージェントとの協働で重要なのは、人間が「普通」や「常識」を知っていることです。AIの創造性は、人間の既存の概念から離れた地点で思考できることに起因しています。だからこそ、人間が「普通」や「常識」を理解していないと、AIの斬新なアイディアの価値に気づけないのです。
AIに「普通」や「常識」を備えさせるのは非常に難しいです。たとえば、私たちが開発した経営者討論AIエージェントは、クライアント企業の経営者の「常識」を学習させたものでした。しかし、このAIエージェントを作ったからこそ、彼ららしい発言をさせることはできても、彼らになりきることはできないということも学びました。
- なぜAIに人間の「常識」を完全に理解させることは難しいのでしょうか。
山口:それは、ある人の経験をすべて言語化し、AIの学習データとすることが不可能だからです。経験は言語化した知識として蓄えられることもありますが、その多くは身体や無意識に刷り込まれたものです。またメディアに多く露出する経営者は、社内向けの顔とは別に社外向けの顔を自己プロデュースしているケースも多く、これもAIによる「人間の常識」の理解を妨げています。
深く生きて、世の中の「普通」や「常識」を知り、それらが作り出したレールに従ったり、あるいは葛藤したりするのは人間にしかできないこと。その経験がAIとの協働には欠かせません。

しかし現代のデジタル時代では、SNSで短尺動画を次々と視聴するような情報の取得が増えています。クイックな情報取得にはその良さがある一方、その分、深く物事を考えて理解しようとする機会が奪われているともいえるかもしれません。今の便利な時代は、知識を得る過程での不便が生み出していた発見や洞察を希薄にしてしまう側面もあります。
そのうえ、With AI時代に突入し、AIによってうわべだけの議論や回答を大量に生成することが可能になりました。机上の空論はAIに任せることができる今、人間にとっては現実世界で実際に感じたことの価値が大きくなっています。
- 確かに現代のAIは相当に発達したとはいえ、そのアウトプットには人間ならではの深みに欠けると感じることも多いです。
山口:AIのアウトプットには示唆に富むものが多い一方、「うわべのあるある」に終始した表面的な内容だったり、逆に現実からかけ離れた回答だったりすることも少なくありません。それらは、一見、創造性のある回答に見えても、実際のマーケティングでは使えない「嘘」になってしまいます。なぜなら、生きた人間の感覚に結びつかないからです。
「深く考えるAI」が考え抜いた答えに対し、人間が現実を生きる感覚を基盤にして疑問や違和感を覚えることが大切です。そうした違和感は実際の調査や仮説検証の実施につながっていくでしょう。そうすれば、単なる「うわべのあるある」ではなく、人々の感情に紐づくマーケティングを考えられるようになるはずです。
- 前回の記事では「With AI時代に求められるのは人間の感情を揺さぶること」と話していました。昨年からAI技術がさらに進歩した今、その考えに変わりはありませんか。
山口:変わりません。「人間の感情を揺さぶる」というのは、言い換えれば「普通」や「常識」を揺さぶることです。AIは「人間にとっての普通」を知りません。だからこそ、マーケターには「人間にとっての普通」を探し出す力が求められます。広告で人の感情を揺さぶるには、人間が深く生きてきた感覚をマーケティングに反映する必要があります。AIエージェントの創造性を活かしつつ、人間の感情を揺さぶるには、私たち自身が人間として深く生きることが大切なのです。
<プロフィール>
株式会社Hakuhodo DY ONE
AI戦略開発室 室長
山口 俊亮

2016年にデータコンサルタントとしてキャリアをスタートし、分析基盤の構築やレポート支援を担当。その後、大型クライアントのデジタルマーケティング戦略設計を手掛け、2017年にはCM×デジタルの横断計測技術を提案し、社内での業績を評価される。2019年から2022年には商業施設向けのマーケティングDX支援をおこない、データ基盤構築や販促施策を推進。2023年からは「IREP LLMs PLAYGROUND」のプロジェクトリーダーとして、大規模言語モデルを活用したマーケティングプラットフォームを開発。2024年度からは「パフォーマンスAI戦略室」と「AI戦略開発室」の室長として、広告領域でのAI活用の推進を担当している。
この記事の著者
DIGIFUL編集部
「DIGIFUL(デジフル)」は、株式会社Hakuhodo DY ONEが運営する「デジタル時代におけるマーケティング」をテーマにした、企業で活躍するマーケティング担当者のためのメディアです。
当社がこれまでに得たデータや経験から、具体的事例・将来展望・業界の最新注目ニュースなどについて情報を発信しています。ニュースやコラムだけでなく、日常業務や将来のマーケティング施策を考えるときに役立つダウンロード資料や、動画で学べるウェビナーコンテンツも随時追加していきます。
デジタルマーケティングの最新情報や知見を得るための信頼できる情報源の1つとしてお役立てください。
「DIGIFUL(デジフル)」は、株式会社Hakuhodo ...