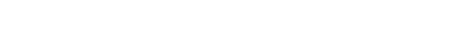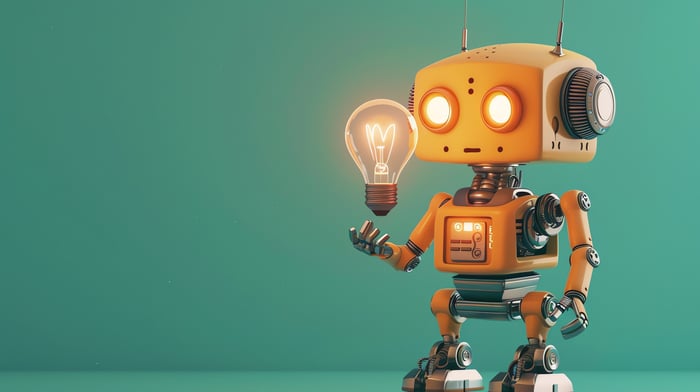
生成AIの活用が企業の新たな成長エンジンとして注目されるなか、生成AIを活用するための環境整備から推進へと移行することが求められています。今回は、組織的な生成AI活用の現実と、活用の推進を実現する「ノリの醸成」の重要性について紹介します。
※本記事の一部は、当社内で開発・運用をおこなう生成AIツール「HAKUNEO」を活用して生成されました。なお、最終的な記事内容の確認・編集はDIGIFUL編集部がおこなっております。
▼人間執筆記事(執筆~編集まで、生成AIを一切活用せずに作成)
▼比較検証記事(生成AI執筆と人間執筆の差分を記事の質や業務効率の観点で比較しています)
生成AI活用の環境整備から活用推進へ
多くの企業が生成AIの導入を進め、基盤の構築やガイドラインの整備を終えた段階にあります。しかし、生成AIを業務で活用できる環境が整ったからといって自動的に活用が進むわけではありません。業務への「定着」と「効率化」が実現されなければ、AIの本来の価値は発揮されないのです。
現場では、「AIは難しくて使いこなせない」「結局変わらない」という声が聞こえてきます。これが意味するのは、環境整備を終えただけでは、生成AI導入の目標である業務効率化や新たな価値創造には至らないということです。生成AIの真の効果を引き出すためには、組織全体の取り組みとして活用の推進を進める必要があります。
生成AI活用の環境整備は大きな第一歩ですが、次の段階として組織全体でAIの利用を促進し、その活用を定着させるための戦略が求められます。具体的には、従業員が生成AIに対する理解を深め、日常業務の中で自然に使いこなすことが必要です。ここで重要なのは、単に技術的な導入だけではなく、組織の文化として生成AI活用を根付かせることです。
生成AIの真の力を引き出すためには、組織全体の意識改革が不可欠です。生成AIの導入が進むと、従業員が自発的に生成AIを活用する動きが広がり、その結果、業務プロセスの革新や新たなビジネスモデルの創出が可能になります。AI活用の先にあるのは、従業員が「人間にしかできないクリエイティブな挑戦」に集中できる未来です。
生成AI活用の鍵を握る「ノリの醸成」
生成AIの活用を推進するにあたり、目に見えないが決定的な要素、それが「ノリ(Momentum)」です。このノリは、従業員の熱意や積極性、生成AIについての日常的な会話の頻度などに反映される、組織の「気運」ともいえるものです。
企業は、生成AIの導入を進めるうえで、4つの変革レイヤー(Human, Operation, IT, Structure)にアプローチする必要がありますが、これらのレイヤーを支えるノリが欠けてしまうと、組織変革は頓挫するリスクがあります。特に、Layer 5とされる「ノリの醸成」は、DX(デジタルトランスフォーメーション 以下、DX)推進の成否を左右する分水嶺となるのです。

生成AIの導入を進めるうえで、多くの企業が直面する課題は、技術的なハードルだけではありません。むしろ、文化的な側面や従業員の心理的な抵抗が大きな壁となることが多いのです。現場において、「AIはまだダメだ」という声が上がる理由は、技術そのものへの理解不足や、生成AIの可能性を実感できないことに起因します。これを克服するためには、組織内にノリを生み出すことが必要です。
例えば、AI導入に成功した企業では、従業員が積極的に生成AIを活用し、成功事例が生まれることでさらに活用が進む好循環が生まれています。このような成功体験が、組織全体のノリを生み出し、生成AI導入の効果を実感させるのです。

生成AIの活用が単なる業務効率化の手段にとどまらず、組織の文化として定着するためには、このノリが不可欠です。
ノリの醸成が欠ける場合、そのリスクは明らかです。AIの導入が形骸化し、「やはり生成AIは難しい」という負の感情が組織内に蔓延し、DX推進に対する抵抗感が高まってしまいます。このような状況では、たとえAIの導入が技術的に成功していたとしても、その価値を組織全体で享受することは難しくなります。従業員が生成AIの利用を避けたり、上層部がその効果に対して懐疑的になったりすることで、最終的には生成AI活用のプロジェクト全体が停滞してしまうのです。
ノリの醸成は単に「楽しさ」や「やる気」を引き出すだけではなく、組織全体のAIに対するポジティブな態度、継続的な学習や適応の姿勢を育てることにつながります。これは、企業が競争力を維持し、さらに成長するために欠かせない要素です。ノリを醸成することで、従業員は新しい技術を学ぶ意欲を持ち、生成AIが日常業務の中に自然と溶け込む環境が整います。
ノリを生むフレームワーク「CAPSULE」
ノリの醸成には、当社が独自に開発したフレームワーク「CAPSULE」が有効です。CAPSULEは、ノリを生むための7つの要素(CoE & Community / AI’s character / Public relations / Slogan / Use case / Leaders / Event)で構成されています。このフレームワークを活用することで、生成AIの活用を促進するための具体的な手法を提供し、組織全体で変革を支援します。

CoE & Community
生成AIの情報や人材の流通を促進するためのタスクフォースや非公式組織を作り、組織内外の連携を強化します。例えば、生成AIの活用に関する知識や成功事例を共有する場を設け、従業員が自発的に学ぶ機会を作ります。これにより、生成AI活用のハードルが下がると共に、従業員間でのノウハウ共有が促進されます。
AI’s character
生成AIに親しみを持たせるためのキャラクター設定をおこないます。例えば、社内のチャットボットに個性的な名前やキャラクター性を持たせることで、従業員とのインタラクションがよりスムーズになり、生成AIの活用に対する心理的なハードルが下がります。これは、生成AIを単なるツールとしてではなく、チームの一員として認識させる効果があり、従業員が生成AIに対してより親近感を抱けるようになります。
Public relations
AI活用を後押しするメッセージングを社内外に広報します。これは、成功事例を共有することや、AIがもたらすメリットを強調することを目的としています。例えば、生成AIを使った業務改善の成功事例を定期的に社内報で紹介したり、社内イベントで表彰したりすることで、その効果を実感しやすくなります。成功事例が広まることで、従業員の関心度が高まり、生成AI活用の推進力がさらに強まります。組織内での生成AIに対する肯定的な評価が広がることで、従業員の間で「自分たちもできる」という前向きな姿勢が醸成されます。
Slogan
生成AI活用の旗印となるスローガンを作り、組織全体にそのビジョンを浸透させます。スローガンはシンプルで覚えやすい言葉を理想とし、例えば「生成AIと共に未来を創る」や「生成AIで業務を革新する」など、社員が日々の業務の中で意識しやすいフレーズを設定します。これにより、AI活用に向けた統一感や目的意識を持たせ、積極的に活用する動機付けをすることができます。
Use case
シンボリックなユースケースを作り出し、広く口コミを生むための生成AI活用事例を社内で紹介します。これにより、従業員は「うちの部署もできるかも」という自信を持ち、生成AI活用の意欲が高まります。例えば生成AIによるデータ分析で業務効率を大幅に改善した事例や、生成AIを活用した顧客対応で顧客満足度が向上した事例などを取り上げながら、生成AI導入の価値を組織全体で共有することで、自分事化するきっかけを作ります。
Leaders
各所から相談が舞い込むアイコン的な人材を育成します。AI導入を推進するリーダーがいることで、従業員は困ったときに頼ることができ、生成AIを安心して使うことができます。このアイコン的人材は、生成AIに関する深い知識を持つだけでなく、コミュニケーション能力に優れ、他の従業員の相談に乗り、指導をおこなうことができる存在です。例えば、AIプロジェクトをリードするリーダーが、定期的にワークショップを開催し、従業員が生成AIに関する疑問を解決できる場を提供することで、組織全体のAIリテラシーを向上させることもできるでしょう。
Event
例えば「生成AI活用アイデアコンテスト」のように、生成AIに関連した社内イベントやコンテストを開催し、従業員の関心を引き付けます。これにより、生成AI活用に対する興味が湧き、日常業務に生成AIを取り入れるきっかけが生まれます。このようなイベントは、従業員が楽しみながら生成AIに触れる機会を提供し、抵抗感を減少させることが見込めます。
CAPSULEフレームワークの実行においては、各要素が相互に関連し合い、シナジー効果を発揮することが重要です。例えば、CoE & Communityで育成された知識やスキルが、Public relationsやEventでの取り組みを支え、生成AI活用の成功事例を広める基盤となります。また、AI’s characterやSloganを通じて従業員の心理的なハードルを下げることで、Leadersが指導しやすい環境が整い、ノリが醸成されていきます。
これらの要素を組み合わせたCAPSULEフレームワークは、ノリを醸成するための強力なツールであり、組織全体が一丸となってAI活用を進める基盤を提供します。ノリが醸成されることで、従業員は生成AIを使いこなす自信を持ち、生成AIの導入効果を最大限に引き出すことができるのです。
CAPSULEの各要素の実行は簡単なことではありませんが、それぞれの取り組みが組織の文化や従業員の行動に根付くことで、生成AIの導入が単なる技術革新にとどまらず、組織全体のトランスフォーメーションを促進します。これは、企業が長期的に競争力を維持し、変化に柔軟に対応できる組織になるための不可欠なプロセスです。
AIと共創する未来を目指して
生成AIの導入は、単なる技術導入ではなく、組織文化の変革を伴う取り組みです。生成AIがもたらす効果を最大限に引き出すためには、ノリの醸成が欠かせません。CAPSULEフレームワークを通じてノリを醸成し、生成AIと従業員が共に進化する企業文化を築くことが、これからのトランスフォーメーションの鍵となります。
生成AIと従業員が共創することで、企業は新たな価値を生み出し、顧客体験や社会貢献においても大きな成果を上げることが期待されます。今こそ、組織のノリを醸成し、AI活用を推進する時です。私たちと一緒に挑戦してみませんか?生成AI活用の推進にお悩みの場合はお気軽にお問合せ下さい。
監修
株式会社Hakuhodo DY ONE
中原 柊

大手コンサルティングファーム、法人向けSaaSスタートアップを経て、2023年にアイレップに参画。メディア/Webサービス/通信/エネルギー業界を中心に、DX企画、CX改革、事業戦略、販促領域などに携わる。DX部門において機械学習系スタートアップとの協業やメディアでの情報発信等にも従事。その後、社内最速でマネージャーに昇進。SaaSスタートアップでは、法人向け動画制作クラウドソリューションのカスタマーサクセス部長 兼 DXコンサルティンググループとして、カスタマーサクセスの戦略からオペレーション構築を通し、契約更新率の大幅改善を達成。また、新規プロダクトの立ち上げ等を主導。ChatGPTをはじめとしたジェネレーティブAIの社内オペレーション組み込みを力強く推進し、外部セミナー等において情報発信活動にも携わる。主な著書に『DXの真髄に迫る』(共著/東洋経済新報社)がある。
この記事の著者
DIGIFUL編集部
「DIGIFUL(デジフル)」は、株式会社Hakuhodo DY ONEが運営する「デジタル時代におけるマーケティング」をテーマにした、企業で活躍するマーケティング担当者のためのメディアです。
当社がこれまでに得たデータや経験から、具体的事例・将来展望・業界の最新注目ニュースなどについて情報を発信しています。ニュースやコラムだけでなく、日常業務や将来のマーケティング施策を考えるときに役立つダウンロード資料や、動画で学べるウェビナーコンテンツも随時追加していきます。
デジタルマーケティングの最新情報や知見を得るための信頼できる情報源の1つとしてお役立てください。
「DIGIFUL(デジフル)」は、株式会社Hakuhodo ...