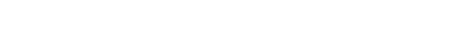With AI時代のマーケティング#03 2025年、獲得型広告クリエイティブ制作のパラダイムシフト

獲得型のデジタル広告クリエイティブは、入稿後、時間とともに成果が悪化する「摩耗」が避けられません。そのため、常に新しいクリエイティブを入稿し続ける必要があり、人的・時間的コストが大きな負担となっていました。しかし今、AIの技術的革新によって、クリエイティブ制作のあり方が大きく変わろうとしています。クリエイティブ制作のパラダイムシフトについて、AI戦略企画室室長の山口俊亮に聞きました。
※本記事の一部は、生成AIツール「Dify」を活用して生成されました。なお、最終的な記事内容の確認・編集はDIGIFUL編集部がおこなっております。
「勝ちパターン」磨きこみの限界
- 従来のクリエイティブ制作は、どのような課題を抱えていたのでしょうか。
山口:
従来の広告クリエイティブ制作は、膨大な労力と人的リソースを要する業務でした。特にデジタル広告においてクリエイティブは「摩耗」が避けられないため、常に新しいものを入稿し続けなければなりません。そのため、企画立案からデザイン、制作、修正などのプロセスを、短いサイクルで繰り返す必要がありました。
当然、そこには大きな人的コストが発生します。限られた予算内で費用対効果を最大化するには、過去の「勝ちパターン」のバリエーションを増やすことが定番の必勝法でした。もちろん当時から多様な訴求を試すことの重要性は、マーケターの間で共通理解となっていました。しかし限られたリソースで成果を最大化するには、過去の「勝ちパターン」を横展開することが現実的な選択だったのです。

- 「勝ちパターン」の横展開には、どのような問題点があったのでしょうか。
山口:
「勝ちパターン」の横展開は、一見効率的に見えますが、実は多くのリスクを孕んでいます。過去に成功した訴求に縛られることで、新しい視点や方法論を取り入れにくくなり、クリエイティブが画一化してしまうのです。現在、クリエイティブはターゲティングにおいて重要な要素となっています。そのため、クリエイティブが画一化すると、訴求の多様性が失われ、ターゲットユーザーが重複してしまうリスクが高まります。その結果、インプレッションの減少やフリークエンシーの過多など、パフォーマンスの低下につながる可能性があります。
また「勝ちパターン」の横展開は、市場の変化や消費者の新たなニーズを見逃す原因にもなります。人間の創造性は「見たもの」「記憶」「考えられること」に限定されるため、どうしても発想が狭まってしまうのです。クリエイターの経験や知識の範囲内でしか発想できず、無限の可能性を探索することができないという限界がありました。

獲得型広告クリエイティブ制作のパラダイムシフト
- 今、獲得型広告におけるクリエイティブ制作の実際のプロセスでは、どのような変化が起きているのでしょうか。
山口:
2025年からクリエイティブ制作のパラダイムシフトというべき変化が始まっています。AIを活用することで、従来のように「勝ちパターン」を磨き込むだけでなく、さまざまな角度で大量
のパターンを試したり、派生クリエイティブを生成したりできる――いわば、クリエイティブ制作を科学的におこなえるようになりました。これにより、マーケットポテンシャルに対して、さまざまなパターンの刺さるクリエイティブを試行錯誤できるようになります。

しかも、大量のパターンをAIで生成すること自体は、人件費という観点では、ほぼゼロコストです。AIによって「考える」コストと「形にする」コストが劇的に低減され、人間は最終的な修正コストのみに集中できるようになったのです。
- 生成AIは2022年頃から広く活用されるようになりましたが、なぜ2025年の今、このパラダイムシフトが起きているのでしょうか。
山口:
このパラダイムシフトを支えているのが、GPT-4oの技術進化です。2025年、OpenAI社は「GPT-4o Image Generation」をリリースし、これまで文章生成で高い評価を得てきたGPT-4シリーズに画像生成機能が加わりました。GPT-4oの画像生成の特徴は「拡散モデル」と「自己回帰モデル」を組み合わせた点にあります。
これまで主流だった拡散モデルが、ノイズから徐々に画像を鮮明にする方法を採用していたのに対し、自己回帰モデルは画像を1ピクセルずつ順に描き上げていきます。自己回帰モデルでは、先に描かれた部分を参照しつつ、整合性を取りながら次のピクセルを設計するため、特に複雑なレイアウトの配置に強みを発揮します。その結果、高い質の広告バナーを生成できるようになりました。

今、 重要なのは「ブランドらしさ」の発掘
- AIがクリエイティブ制作に革新をもたらす一方で、人間が注意すべき点はありますか。
山口:
AIは大量のパターンを生成できますが、真に人間の心を揺さぶる感情表現には、まだ到達できていないのが現状です。AIには、人間のコンテクストや文化的背景を本質的に理解できないという限界があるからです。そこで重要になるのが「ブランドらしさ」の発掘です。
- 「ブランドらしさ」とは、具体的にどのようなものでしょうか。
山口:
「ブランドらしさ」とは、ブランドが持つ本質的な個性や価値観が、生活者との関係性を通じて形成されていくものです。生活者の心の中に形成されるブランドイメージ、企業文化、そして長期的な顧客との関係性が相互に作用しながら築かれていきます。
「ブランドらしさ」は、長年かけて築き上げられた情緒的価値や文化的背景に根ざした「心を動かす力」といえるかもしれません。

- 「ブランドらしさ」をAIに理解させることは難しいのでしょうか。
前回の記事でもお話ししましたが、AIは「普通」や「常識」を理解することが苦手です。特に「ブランドらしさ」は多くが暗黙知として存在します。生成AIは明示的に言語化された情報は処理できますが、言葉にならない感覚や文化的背景に根ざした「らしさ」の本質を捉えることは困難です。データ分析や技術的アプローチだけでは、これらの暗黙知を完全に捉えることはできません。
▼関連記事
担当者間で共有されている無意識の了解事項や、広告会社が長年培ってきた業界特有のトンマナは、すべてを生成AIのプロンプトに正確に落とし込めるものではありません。また、広告主企業が直感も含めて積み重ねてきた判断や、言葉の節々に表れる「企業文化」を言語化し、再現可能な形に整理することは、決して一朝一夕でできることではないでしょう。さらに、広告会社のディレクターだからこそ持ち得る、特定の広告主企業に対して特別に提供してきたクリエイティブへのこだわりもまた、単純に言語化してノウハウ化するには難易度が高い領域です。
人間特有の経験や感情に基づく理解には、人間の視点が不可欠です。

- 実際に生成AIを活用して「ブランドらしさ」を追求した事例はありますか。
山口:
過去にご支援させていただいたあるお客様のプロジェクトでは、まず生成AIによる包括的なデータ分析をおこない、ブランドDNAを抽出しました。
具体的には、ペルソナごとに15分単位でユーザー行動ログを10日分作成し、その商品を購入したい、探したいタイミングを捉えることで、ペルソナ固有のタッチポイントを洗い出しました。さらに、過去3年間のクリエイティブ実績データ、ユーザー行動ログ、市場動向データなど多角的なデータを専用の生成AIにインプットし、詳細分析を実施。「勝ちクリエイティブ」と「負けクリエイティブ」の特徴を定量的・定性的に抽出しました。
この抽出作業により、ペルソナの日常生活の隙間時間がいつあって、どんな気持ちから思い立ってブランドに接触し、離脱するかの、非常に高い解像度で正解者理解が可能になりました。そして、成果として勝ちと判定されたクリエイティブが、どんなデザインや表現、視覚的特徴を持っていたのか、大量のクリエイティブを一つひとつAIが言語化して共通点を見つけてくれました。
ただし、市況感や市場データを収集させた生成AIだけでは、真に人の心を動かすクリエイティブを生み出すことはできません。生成AIが量産したラフ案の中から人間が最適なものを厳選し、必要な修正点を特定します。選別されたクリエイティブは、「ブランドらしさ」という観点から専門のデザイナーによって微調整され、視覚的な一貫性と品質が担保されます。
最終的な判断はブランドの本質を深く理解した人間がおこなうことで、AIの技術と人間特有の文脈理解・感性を最適に組み合わせたクリエイティブ制作が実現するのです。
AIによる大量のパターン生成とその課題
- 大量のパターン生成は「ブランドらしさ」の醸成にどのように寄与するのでしょうか。
山口:
現在、世の中で普及しているクリエイティブ生成AIツールでは、勝ちパターンの量産にとどまり、似たようなクリエイティブが多くなる「クリエイティブ硬直化」が起きているケースが多くみられます。
しかし、当グループが独自開発・活用するCREATIVITY ENGINE BLOOMを中心とした生成AIツールは、勝ちパターンの単純な量産だけでなく、Who・What・Howという広告クリエイティブの基本設計そのものから新たに発想します。ですから、大量のパターン生成が可能であり、制作物が均質化せず、広告効果の低下を防ぐことができます。
そして、その大量の選択肢の中から、人間の感性によってブランドにふさわしい表現を選び、磨き上げていくことで、「ブランドらしさ」が単一の型に固定されることなく、より豊かで立体的に伝わっていくのです。大量のパターン生成は「ブランドらしさ」を育む土壌を提供しているといえるでしょう。

- 今後、AIを活用したクリエイティブ制作において、どのような課題が考えられますか。
山口:
AIの生成速度に人間の業務が追い付かなくなる状況が生じる可能性があります。AIにより無数のクリエイティブバリエーションが作成可能になった一方で、それらを実際に広告プラットフォームへ入稿する作業が新たなボトルネックになっています。
大量のクリエイティブをチェック・分析・登録する作業は、従来の人的リソースでは対応しきれない規模となっており、効率的な運用体制の構築が急務です。プラットフォームごとに最適化された入稿方法が異なるため一元管理が難しく、クリエイティブチェック、配信設計、入稿指示に至るまで、オペレーション全体をAIエージェント化していく必要があります。
今後は、クリエイティブ制作の全体的な流れそのものを見直し、人間とAIがそれぞれの強みを活かして効率的に協業できる業務フローを新たに構築する必要があるでしょう。
<プロフィール>
株式会社Hakuhodo DY ONE
AI戦略開発室 室長
山口 俊亮

2016年にデータコンサルタントとしてキャリアをスタートし、分析基盤の構築やレポート支援を担当。その後、大型クライアントのデジタルマーケティング戦略設計を手掛け、2017年にはCM×デジタルの横断計測技術を提案し、社内での業績を評価される。2019年から2022年には商業施設向けのマーケティングDX支援をおこない、データ基盤構築や販促施策を推進。2023年からは「IREP LLMs PLAYGROUND」のプロジェクトリーダーとして、大規模言語モデルを活用したマーケティングプラットフォームを開発。2024年度からは「パフォーマンスAI戦略室」と「AI戦略開発室」の室長として、広告領域でのAI活用の推進を担当している。
この記事の著者
DIGIFUL編集部
「DIGIFUL(デジフル)」は、株式会社Hakuhodo DY ONEが運営する「デジタル時代におけるマーケティング」をテーマにした、企業で活躍するマーケティング担当者のためのメディアです。
当社がこれまでに得たデータや経験から、具体的事例・将来展望・業界の最新注目ニュースなどについて情報を発信しています。ニュースやコラムだけでなく、日常業務や将来のマーケティング施策を考えるときに役立つダウンロード資料や、動画で学べるウェビナーコンテンツも随時追加していきます。
デジタルマーケティングの最新情報や知見を得るための信頼できる情報源の1つとしてお役立てください。
「DIGIFUL(デジフル)」は、株式会社Hakuhodo ...