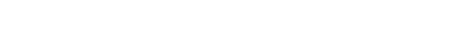ブランドマーケティングにおいてデジタル広告の配信成果を事業成果に結びつけることは容易ではありません。デジタル広告のKPIは達成しているにもかかわらず、ブランドリフトや売上拡大といった事業成果につながらないことに悩んでいる方も多いのではないでしょうか。その理由の一つに、生活者行動の変化を十分に反映していないマーケティング設計が挙げられます。Hakuhodo DY ONEと株式会社NTTドコモ(以下、NTTドコモ)は、生活者行動を改めて考察し、Meta広告を中心に、デジタル広告のブランドキャンペーンを活用して売上拡大を実現しました。本記事では、事業成果に繋がる広告施策の正しいKPI設計の考え方について、NTTドコモの実施内容を踏まえて具体的にお伝えします。
生活者の態度変容につながるKPIを求めて
NTTドコモでは、携帯電話サービスを中心とした通信事業に加え、金融・エンタメ・ヘルスケアなどの生活を豊かにするスマートライフ事業を幅広く展開しています。なかでも、スマートフォン端末販売におけるブランドキャンペーンにおいては、KGIとして「スマートフォン端末の利用意向リフト」、それを達成するための広告運用のKPIには「視聴完了数」を設定し、動画広告を活用しながら「視聴完了数」の最大化に努めてきました。しかし、キャンペーンを実施する中で、大きな課題が浮かび上がります。広告運用のKPIは達成しているものの、KGIである「利用意向リフト」率は鈍化傾向にあったのです。
KPIである「視聴完了数」の目標値は今のままでよいのだろうか――この疑問は、KPIの妥当性を問い直すだけでなく、コミュニケーション設計全体を見直すきっかけへとつながりました。それは、動画の視聴完了だけが真に生活者の態度変容を促すのかという問いを生み出したためです。

縦型ショート動画の普及と生活者行動の変化
もちろん生活者の態度変容を促すうえで、動画の視聴完了は重要です。なぜなら動画を最後まで見てもらうことで、メッセージを伝えることができ、商品やサービスの特徴の深い理解につながりやすいためです。そして商品やサービスの理解は比較検討の際の材料となり、購入段階において自社ブランドが選ばれやすくなります。そのため現在も「視聴完了数」は、生活者の態度変容を促せたかを測る運用指標として有効だといえます。

しかし生活者の行動変化に伴い、この指標の使い方もアップデートが求められています。近年、Instagramリールをはじめとした縦型ショート動画プラットフォームが急速に普及しています。こうしたプラットフォームでは、15秒程度の縦型ショート動画を次々とスワイプして流し見することで、大量の情報を素早く受け取ることができます。
NTTドコモにおいても、生活者の深い商品理解を目的とした「視聴完了数の最大化」というKPIをアップデートし、現代のクイックな情報取得行動に適したものにしていく必要がありました。

生活者行動の変化を加味したKPI再設計へ
そこでNTTドコモでは、KGIである「利用意向リフト」から逆算式に広告運用のKPIを再設計しました。広告配信結果と利用意向リフトの関係を分析した結果、「視聴完了数」の最大化が必ずしも利用意向リフトの向上に直結するわけではないことが明らかになりました。そのため、分析結果において利用意向リフトと相関のあった「視聴完了数÷フリークエンシー」の数値を「視聴完了リーチ」と名付け、それをもとに運用KPIである視聴完了数を算出し直しました。

「視聴完了リーチ」は、視聴完了とともに、より多くの生活者にリーチすることを意図したものです。従来のキャンペーンにおいてKPIの目標値はリーチ数を加味せずに算出し、「視聴完了数」を最大化することを目指していました。そのため動画の内容の深い理解を促すことはできても、広範なターゲットへの動画配信には限界がありました。
近年の情報収集行動の変化を考慮すると、KPIにリーチの視点を加えることは重要です。なぜならクイックな情報取得が広まりつつあるということは、仮に短時間であったとしても、生活者の情報取得サイクルにおいて自社ブランドを認知してもらう機会が増えていることを意味するためです。より多くの生活者の情報収集行動の中に自社ブランドを組み込み、認知と共感を得ることができるならば、購入段階で自社商品が想起される確率は高まるでしょう。
縦型ショート動画を活用したフルファネル戦略
KPI設計の際に「リーチ」を加味したことで、視聴完了を目指すだけでなく、より多くの人に広告を届けるための施策も積極的に進められるようになりました。その一例が、さまざまな縦型動画プラットフォームを活用したフルファネル戦略です。
それまでは、「視聴完了数」の最大化をKPIとして、YouTubeやTVerなどスキップできない横型動画広告を中心に配信していました。しかし、この方法では出稿先のメディアが限られ、広告のリーチ拡大に頭打ちが生じてしまいます。
そこで新たなキャンペーンでは、InstagramリールやTikTok、GumGum、Pinterest、YouTube Shortなど、複数の縦型動画プラットフォームを活用しました。これにより、従来の横型動画ではリーチできなかった新しいユーザー層にもアプローチできるようになりました。
配信方法にも工夫を加え、カスタマージャーニーに沿ったフルファネル戦略を展開しています。具体的には、まず15秒の縦型ショート動画で認知・興味を獲得し、視聴者にはリターゲティングで長尺動画を配信して理解を促進、さらにコンバージョン最適化したディスプレイ広告で購入を後押しする流れを構築しました。
このように、認知から興味・理解、そして購入促進まで、縦型ショート動画を中心に幅広いユーザーに効果的にアプローチできる戦略を実現しています。

この結果、KGIである利用意向リフトはキャンペーン開始から1ヶ月で前の端末モデル比で127%、2か月で130%と大幅に向上。また発売後1か月の販売台数も前モデル比で114%を記録しました。加えて、利用意向リフト上昇には認知動画だけでなくディスプレイ広告のバナーも寄与していることが確認され、動画で起用したタレントを静止画でも中央に配置するなど、静止画バナーにおけるクリエイティブの作りこみの重要性が示唆されました。
生活者の心理は日常生活の中で連鎖的に変化していくものです。そのため、配信したブランディング広告がどれだけ生活者の態度変容に寄与できたのかという評価は、定性的にはもちろん、定量的な指標に落とし込むことは容易ではありません。加えて生活者行動も日々変化していきます。広告配信の成果を事業成果に結びつけるためには、AIも活用した生活者インサイトの深掘りや広告効果の可視化、プラットフォームやマーケティングファネルごとに最適化したクリエイティブ制作なども重要です。今後もHakuhodo DY ONEでは生活者行動の変化と企業課題に合わせて継続的にプロモーション戦略を改善し、広告主の事業成長に貢献していきます。
この記事の著者
DIGIFUL編集部
「DIGIFUL(デジフル)」は、株式会社Hakuhodo DY ONEが運営する「デジタル時代におけるマーケティング」をテーマにした、企業で活躍するマーケティング担当者のためのメディアです。
当社がこれまでに得たデータや経験から、具体的事例・将来展望・業界の最新注目ニュースなどについて情報を発信しています。ニュースやコラムだけでなく、日常業務や将来のマーケティング施策を考えるときに役立つダウンロード資料や、動画で学べるウェビナーコンテンツも随時追加していきます。
デジタルマーケティングの最新情報や知見を得るための信頼できる情報源の1つとしてお役立てください。
「DIGIFUL(デジフル)」は、株式会社Hakuhodo ...