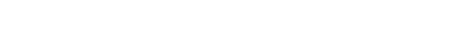日々の情報収集でWebサイトを見ていると、スクロールする際にたくさんの広告が目に入りますよね。そのなかで、意識してしっかり見ている広告はどれくらいあるのでしょうか?情報過多な現代において、広告が本当にユーザーに届いているのか、広告投資の効果をどう最大化するか、多くのマーケターが頭を悩ませています。広告がどれだけ注視されたかを可視化し、施策の成果を正しく評価することは、投資額を検討するうえでとても重要です。その解析に役立つのが「Attention計測」です。Attention計測を活用することで、キャンペーン実施中にリアルタイムで運用の調整ができたり、ブランドリフトの向上を短期間で実現できたり、さまざまなメリットがあります。本記事では、Attention計測の基本から実際の活用方法までをわかりやすく解説します。
Attention計測とは
Viewablity(ビューアビリティ)との差分
Attention計測とは、Web上の動画広告・ディスプレイ広告(以下、広告)について、ユーザーが本当に注視して見ているかどうかを計測する手法です。
似た指標に「Viewablity」がありますが、こちらについては視認可能な場所に広告が表示されたかどうかはわかっても、ユーザーが注視しているかは分からないという問題点がありました。つまり、広告は画面上で流れているが、ユーザーがデバイスの前にいなかったり、目を離していたとしても、感知することはできなかったわけです。
これに対してAttention計測では、広告の表示時間や画面占有率、反応率等を分析し、実際に注視しているかどうかを計測していきます。その結果から、どれだけユーザーに広告が届いているかを高精度で判定します。
このような「どれくらい見られているのか」まで算出できる強みが評価され、世界中で導入が進んでいます。

代表的な計測手法
Attention計測には大きく2つの計測手法があります。一つはアイトラッキングデータをもとに計測する手法です。パネル(調査を担当するアンケート要員)に専用デバイスを装着し、視線データを収集することで、広告の注視度を算出します。Lumen社が代表的な提供会社として知られていますが、残念ながら2025年4月現在、国内ではこの専用デバイス及びパネルを提供している企業が存在しないため、この手法でAttention計測を活用できる媒体には制限があります。現在国内で活用しやすい手法は、ユーザー行動から分析する方法です。こちらは広告に対する反応率(画像を拡大縮小したか、マウスオーバーしたか等)を算出し、これらの指標を統合的に評価することで広告の注視度を算出します。本手法を扱う代表的な会社としてDoubleVerify社が存在します。
Attention計測の統合指標はAttention indexと呼ばれ、以下のような要素で構成されています(ここでは、DoubleVerify社が提唱する指標を紹介します)。
Exposure index(露出)
実際に広告がどのくらい表示されたかを表し、Prominence index(画面占有率など)やIntensity index(ビューアブルタイムなど)をもとに数値を算出します。
Engagement index(接触)
ユーザーが広告へどの程度接触したかを表し、User Presence index(ユーザーが存在するか)※1、Ad interaction index (反応率)※2をもとに数値を算出します。
※1:User Presence index (ユーザーが存在するか)…スクロールした割合、デバイス上でキーを押した割合、マウスカーソルを動かした割合など
※2:Ad Interaction index(反応率)…ユーザーがマウスオーバーした割合、広告を触った割合、広告をクリックした割合など
今回紹介した以外にもさまざまな指標があり、総合的に判断してAttention indexを算出します。一言にAttention計測といっても複数の計測ロジックがあり、大まかにいうと「アイトラッキングデータからAttentionを定義しているのか」「行動データでAttentionを定義しているのか」の2種類があるということ理解しておきましょう。
なぜ Attention 計測が必要なのか
Cookieに依存することなく計測ができる
Google がCookie廃止を撤回したことで、Cookieを活用したユーザーの行動データはこれまで通り取得することができます。しかし、改正個人情報保護法の施行やプライバシー保護の観点から、データの取り扱いに対する規制は年々厳しくなっています。加えて、生活者データの取扱に対する法規制の強化、ブラウザ・OS提供事業者による技術規制の強化、Apple・Google 等のブラウザ /OS ベンダーによるブラウザおよびアプリでのユーザー識別子の利用制限などがあり、従来のようにCookieを活用することでマーケティング精度を高めるのが難しい状況になってきました。こうした背景から、Cookieデータに頼らない「Cookie時代の計測手法」として、Attention 計測に注目が集まっています。

認知施策の効果をスピーディーに可視化。高速PDCAを実現できる
認知施策の効果計測は、ブランドリフトサーベイ※3(以下、BLS)を活用することが一般的です。媒体付帯のBLS(動画の合間にアンケートが表示されるものが代表例)や第三者の調査会社に依頼することで計測を実施しますが、キャンペーン事後の調査であることから、リアルタイムでの効果測定ができないという課題があります。意識指標をリアルタイムで測定できないからこそ、キャンペーン実施中にブランドリフトを最大化させるような運用調整はできませんし、また、1回目のキャンペーンと2回目の実施までのリードタイムが短い場合は、1回目のキャンペーン事後調査で得られた示唆の反映が2回目のキャンペーンに間に合わないという事象が発生しがちです。
一方、Attention計測では、リアルタイムにユーザー行動を計測するため、キャンペーン期間中の運用調整が可能です。「PDCAのスピード」に課題感をお持ちであれば、 認知施策の効果をスピーディーに可視化する手段としてAttention 計測が有用となります。
※3:ブランドリフトサーベイ…アンケートによるブランドの認知度の調査

Attention計測の活用
ブランドリフト施策と相性が良い
前述の通り、BLSはキャンペーン事後の調査であり、デジタル広告の運用指標として活用することはできません。 そのため、リーチを広げれば良いのか、フリークエンシーを重ねればよいのか、動画を最後まで見て貰えば良いのか、どの指標がブランドリフトの好転につながるのかが不明瞭なケースも珍しくなく、マーケターにとって悩みの種となっています。
しかし、Attention計測の登場によって、暗中模索で認知施策を実施する時代は終わりを迎えるかもしれません。「Attentionが高い広告施策はブランドリフト効果も高い 」という相関関係があることが、リサーチ会社の調査によって明らかになっており、認知施策におけるデジタル広告のKPIとしてAttentionを活用することは有用だと考えられます。
また、認知施策だけでなく、見込み顧客に向けた興味喚起施策においてもAttentionは活用の余地があります。ニーズが顕在化していない見込み顧客の利用意向を高めることを目的として、生活者のインサイトを捉えた注意を引くような訴求を行ったとしても、割引やプレゼントがついた"分かりやすい"オファー訴求と比較するとCTRが低く、クリエティブとして評価されないケースがあります。しかし、CTRが低くとも、「見込み顧客の注意を引き、利用意向を引き上げる」という目的においては、必ずしも広告効果が薄いとはいえず、そうした場合には、AttentionはCTRの一歩手前の指標として活用できるかもしれません。
主な分析軸はクリエイティブ・プレースメント・ターゲティング
マーケティング施策の効果計測は、マーケティング施策全体(広告以外の施策含む)、広告施策全体、デジタルメディア全体、個別デジタルメディアの最適化など、さまざまな区分けがありますが、Attention計測はどこをカバーしているのでしょうか。
現在、Atention計測がカバーしているのは、デジタルメディア全体および個別デジタルメディアの最適化です。
主な分析軸は、クリエイティブ(どんな訴求内容か)やプレースメント(どこに出稿するか)、ターゲティング(誰に広告を訴求したいか)の3つで、たとえば、基準に満たないプレースメントは配信期間中に順次停止対応するというアクションが考えられます。
今後の見通し
これまでご説明した通り、Attention計測を活用すれば、広告の注視度に関する実態を把握することができます。広告の注視度がどの程度ブランドリフトに結びついているのか、その相関や貢献度に関する検証を重ねていくことで、確からしい「メディア横断指標」として活用できるようになるはずです。メディア横断指標として活用できれば、Attentionを基に、より効果のあるメディアに予算をアロケーションするという動きも活発になるでしょう。
Attention計測を活用したブランドリフト広告のマーケティングにご興味がありましたら、ぜひ当社までご相談ください。
この記事の著者
鳴瀧 拓未
2022年に株式会社アイレップ(現 株式会社Hakuhodo DY ONE)に新卒入社。メディアプランナーとして初期配属後、BtoC業種を中心にメディアプランニングに従事。その後、ストラテジックプランナーも兼任し、全体戦略を踏まえたメディア戦術への落とし込みなどを担当。現在は、メディア・ストラテジックプランナーでの経験を活かしつつ、施策の正確な評価とPDCAスキームの構築を強みとしてクライアントの中長期的なビジネス成長に貢献。
2022年に株式会社アイレップ(現 株式会社Hakuhodo...
関連動画
関連記事
「サステナブルなマーケティング」がもたらす持続的な成長のあり方 Hakuhodo DY ONEが研究発表
2024.12.06
#マーケティング
#データ分析
#AI
#動画広告
#クリエイティブ
#広告
#越境するダイレクトクリエイティブStudio
#突破する動画Studio
#TEAM JAZZ
#没入するエンタメStudio
#常駐型コンサルティング
#令和シニア研究所
#サステナビリティ
#アニメーション広告
#web3.0
#クリエイティブ法務